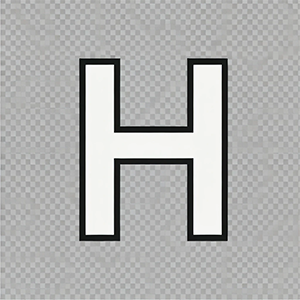Article
デッキ紹介・解説やメタゲームブレイクダウンなどはもちろん、
単なる攻略情報以外もお届け
NEWEST
最新記事
-

【今週のピックアップデッキ】アゾリウスブリンク/ボロス召集/ティムールスケープシフト
こんにちは。 細川 侑也(@yuyan_mtg)です。 今週のピックアップデッキでは、ちょっと珍しいデッキを、軽い解説を交えて紹介していきます。 紹介デッキ アゾリウスブリンク ボロス召集 ティムールスケープシフト アゾリウスブリンク スタンダードリーグ : 5-0 By DB_Dykman MTGアリーナ用インポートデータ クリーチャーを一時的に追放して、「戦場に出た時」の能力を何度も使い回す。この戦略を主体とするデッキの総称は、《一瞬の瞬き》の英語名にちなんでブリンクと呼ばれています。 初代《一瞬の瞬き》はフラッシュバック付きの優秀なブリンクで、《裂け目翼の雲間を泳ぐもの》や《造物の学者、ヴェンセール》で相手の土地を戻し続けたり、《目覚ましヒバリ》をブリンクさせて一気に2体リアニメイトし、スタンダードで大活躍していました。 最近ではモダンでブリンク内蔵クリーチャー《溌剌の牧羊犬、フィリア》で《ベイルマークの大主》を明滅させるオルゾフブリンクが躍動していますね。 そんな歴史あるアーキタイプ、ブリンクがスタンダードに帰ってきました! まずは肝心のブリンクカードから紹介していきましょう。 いつの間にか採録されていた《魅力的な王子》はブリンク以外にライフゲインと占術を持つ便利なクリーチャー。自身がブリンクカードでありながら、ブリンクを受ける対象としても使えるのが嬉しい。 《忠実な馬、フォーチュン》は騎乗したクリーチャーと自身の2つをブリンクできる乗騎。戦場に出た時に占術2のオマケがあるので、ドローの質を高めながら横のクリーチャーを使い回せます。 『久遠の終端』から入った新しいブリンククリーチャーが《万物の定めを追う者》。戦場を離れるまでクリーチャーを追放するのですが、ワープで唱えるとターン終了時に《万物の定めを追う者》が戦場を離れるので、実質ブリンクです。通常キャストした際は除去としても機能してくれます。さすが暗殺者。 そしてブリンクスペルは《水飛沫の門》!1マナですがソーサリーとそこそこのデメリット。しかし、鳥か蛙かカワウソかネズミをブリンクさせていた場合は1ドローできます。このデッキには1種だけ蛙クリーチャーがいるので、ただの1マナブリンクでない時もあります。 その蛙が《陰気な港魔道士》。他のクリーチャーが死亡せずに戦場を離れていたら1ドローできる蛙で、ブリンクとの相性が最高です。クリーチャーをブリンクするたびに1ドローですからね。《忠実な馬、フォーチュン》などで2体同時に戦場を離れた場合は1ドローしかできませんが、それでも十分。 2マナを支払うと自分のクリーチャーを手札に戻せるので、1ドローしながらそのクリーチャーを戦場に出して再利用できます。 さあ、充実したブリンク陣を見てもらった後は、ブリンク対象となるクリーチャーを見てみましょう。 まずは《量子の謎かけ屋》!今やスタンダードのみならずモダンでも第一線で活躍するスフィンクスですが、戦場に出た時に1ドローできるので、当然ブリンク対象です。手札がなければブリンクで1ドローが2ドローになり……あっという間に手札が回復していきます。 そしてこちらは戦場に出た時ではなく、離れた時に誘発する《反因果の残留》。戦場を離れた時にカードを引いて、その後にコントロールしている土地の数以下のマナ総量のパーマネントをタップ状態で出せます。土地を伸ばして良し、クリーチャーを叩きつけても良しの良質なエルドラージ。 本来はワープで能力が誘発し、その後は死亡時にもう1度誘発する程度のエルドラージなのですが、ブリンクで何度も能力を使い回せるので、このデッキでは一度戦場に出して放置すると大変なことになります。 更に《量子の謎かけ屋》と《反因果の残留》はいずれもワープを持つクリーチャーなので、ブリンクとの相性はぴったりです。ワープはエンド時に追放される代わりに本来よりかなり軽いコストに設定されています。なので、ワープ状態のクリーチャーをブリンクしてそのまま場に定着させる行為は、実質的な踏み倒しとなるのです。 3ターン目に《忠実な馬、フォーチュン》、4ターン目に《反因果の残留》をワープで出して《忠実な馬、フォーチュン》に騎乗して攻撃すると、《反因果の残留》が誘発しながらパーマネントを展開し、最終的に《反因果の残留》が戦場に降り立つことになります。 同じワープ持ちの《星原の歌手》は、戦場に出た時の誘発を倍にします。《魅力的な王子》で4点ゲインしたり、同時に2体をブリンクしたり、《量子の謎かけ屋》で2枚引いたりと、やはり放置すれば大暴れ。《反因果の残留》とは何のシナジーもありませんが贅沢は言えません。 一度動き出すとアドバンテージが止まらなくなるのがブリンクデッキの良いところ。回していてすごく楽しいので、普通のマジックに飽きた方はぜひお試しください。 コスモジャンド パイオニアリーグ : 5-0 By hauterho MTGアリーナ用インポートデータ 小粒なクリーチャーを展開して召集クリーチャーを出して相手をなぎ倒す、横並びビートダウン、ボロス召集。 スタンダードでも活躍したデッキですが、パイオニアの召集は一味違います。 スタンダードではクリーチャーを並べた後の召集カードが《イーオスの遍歴の騎士》でした。クリーチャーを2枚加える強力なカードではありますが、速効性があるわけではありません。 それがパイオニアになると大きく変わります。《イーオスの遍歴の騎士》と同じく、5マナの召集持ちのクリーチャーがもう1種増えるのです。それが《敬慕されるロクソドン》。 しかもその能力は《イーオスの遍歴の騎士》と違い超攻撃的。召集のためにタップしたクリーチャーの上に+1/+1カウンターを1個ずつ置いていくのです。2ターン目に《敬慕されるロクソドン》を出しながら2/2の群れが5体並ぶ恐ろしい場が完成します。 と、ここまでは昔から変わりません。今回なぜボロス召集を紹介したのか?その答えは、『久遠の終端』でとあるカードが入って強化されたからです。 それが《コスモグランドの頂点》! スタンダードでもエスパーピクシーで採用されていたクリーチャー。2回呪文を唱えるとトークンを生成したり、全体強化を行います。このカードがボロス召集と相性が良いことに気が付いたプレイヤーは天才ですね。 まず召集は非常に軽いデッキ。1マナのカードが大半ですし、《羽ばたき飛行機械》に至っては0マナ。3ターン目に《コスモグランドの頂点》を出してそのまま誘発までいけます。 召集クリーチャーたちも場合によっては0マナになるので、やはり3ターン目に《コスモグランドの頂点》を出しながら《イーオスの遍歴の騎士》と繋げて、そこから《コスモグランドの頂点》が誘発します。 そして《コスモグランドの頂点》の能力がどちらも召集と相性が良いのもポイント。横に広げたければトークンを生成すれば良いし、十分にクリーチャーがいるなら全体強化で次のターンの勝利を狙えます。 この3マナのスロットには《イモデーンの徴募兵》が入っていることが多かったと思います。全体強化しつつ速攻を付与するこのカードはフィニッシュの瞬間には効果的ですが、腐る場面もそれなりにありました。クリーチャーが足りなければ中途半端なダメージしか入りません。 しかし、《コスモグランドの頂点》はトークン生成に全体強化と、場面を選ばずに活躍できるカードです。《イーオスの遍歴の騎士》で《コスモグランドの頂点》と1マナクリーチャーをセットで拾われた時の絶望感と言ったらないでしょう。 《ひよっこ捜査員》《スレイベンの検査官》の手がかり8枚体制に《イーオスの遍歴の騎士》なので、《コスモグランドの頂点》は意外と2回以上誘発してくれます。ボロス召集という一撃必殺のデッキが、継続的なトークン生成を手に入れたのはかなりの脅威です。 デッキの性質上、単体除去に非常に強いデッキなので、全除去がメインから大量に入っている環境でなければ、ボロス召集は無双するかもしれません。 《コスモグランドの頂点》の頂点たるゆえん、戦えばわかるはず! ティムールスケープシフト モダンゴールドリーグ : 5-0 By ilGianB1 土地を7枚置いて《風景の変容》を打つと勝利する。モダンにおける《風景の変容》はずっとそんなカードでした。 7枚の土地を生け贄にするとデッキから6枚の《山》と《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》が場に出て、《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》の条件が6枚同時に達成。18点のダメージが飛んで終了。これを《風景の変容》1枚で行えるので、実質スケープシフトは《風景の変容》1枚コンボでした。 《欠片の双子》が《やっかい児》を必要としたり、コンボは基本的には2枚で成立することがほとんど。 その中でたった1枚でゲームに勝利できる《風景の変容》は、人気の土地コンボでした。 しかし現代マジックにおいて、土地をただ7枚並べるという行為は2枚コンボよりもハードルが高い。《風景の変容》と土地7枚を揃えるのは2枚コンボ以上の難易度となってしまい、スケープシフトは現環境からは姿を消しています。 《風景の変容》は《精力の護符》があれば4枚の土地から瞬殺でき、このコンボを擁するアミュレットタイタンは今モダンで最も強いコンボの一つとなっています。2枚コンボに1枚コンボが負けてしまったのです。 《風景の変容》と土地7枚で勝つデッキがモダンで再び脚光を浴びるにはどうすれば良いか?その答えは「速やかに土地を並べる」に他なりません。 そしてそのためのカードが『久遠の終端』で追加されました。その名は《終端探査機》。 1マナ2/2で死亡時にお互いのプレイヤーが着陸船トークンを生成できるというアンコモン。このカードが《風景の変容》に新たな希望を与えました。 着陸船は2マナ起動でライブラリーから基本土地を場に出せるカード。要するに《不屈の自然》を行えるのですが、この着陸船トークンを死亡時に生成するだけの《終端探査機》がなぜ重要なのか? 答えは《耕作の閃光》です。 ライブラリーから基本土地を2枚サーチし、1枚をセットできる3マナのカード。要するに《耕作》なのですが、緑のクリーチャーを生け贄にすることで0マナでキャストできてしまいます。そう、この《耕作の閃光》の生け贄に《終端探査機》はぴったりなのです。 1ターン目に《終端探査機》を出して《耕作の閃光》で生け贄にし、2ターン目に着陸船を起動。これだけで3ターン目に既に5マナが確定するので、1回のマナ加速があればお手軽4ターンキルとなります。 《耕作の閃光》はこれまでもスケープシフトに組み込まれてきましたが、ネックなのは0マナで打つための追加コストでした。緑の軽いクリーチャーは環境にさほど多くなく、マナ加速ができるかもしれない《とぐろ巻きの巫女》やドローできる《氷牙のコアトル》など、不純物となりうるカードを採用せざるを得ませんでした。 その点、《終端探査機》は死亡時に確実に着陸船になるので、まっすぐ《風景の変容》で勝つルートを走ることができます。 《終端探査機》が加わったことで《耕作の閃光》で生け贄にできるクリーチャーが《樹上の草食獣》と合わせて2種となり、1ターン目のキャストがそれなりに安定するようになりました。ようやくモダンで《風景の変容》が《精力の護符》なしでも間に合うようになったのです。 土地を並べて《風景の変容》を打つだけのシンプルなデッキ構成なので、入っているカードも素直なものばかりです。《次元の創世》はマナ加速が必要なら土地を置き、《風景の変容》も探すことができる、まさにこのデッキのためのカード。 《食糧補充》も青いコンボデッキならお馴染みですね。更に土地をたくさん並べるデッキなので、《星間航路の助言》も採用されています。 7枚目の土地を置いて2マナで打ち、7枚の中から《風景の変容》を探してそのまま打って勝つのは美しい流れです。《食糧補充》よりも強い瞬間ですね。 《風景の変容》は4枚しか採用できないため、この手のデッキでは実質《風景の変容》を7枚体制にする《願い》や《白日の下に》などが採用されることがありましたが、ドロースペルが強くなり、《風景の変容》へのアクセスが容易になり、ついにそういった追加の《風景の変容》はすべて抜けました。 《終端探査機》の加入でモダンのスピードに追い付いたティムールスケープシフト!《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》を再び噴火させるときが来ました!
-

モダン最新環境をチェック!安定感を増したコンボデッキたちがエネルギーを襲う!
こんにちは。 細川 侑也(@yuyan_mtg)です。 『久遠の終端』は《ピナクルの特使》をはじめ何枚かモダンに影響を与えるカードが登場しましたが、その中でも最もインパクトを残したのは《量子の謎かけ屋》でした。 その後、モダン環境で《量子の謎かけ屋》は生き残っているのでしょうか?そして他の注目のカードたちは使われているのか? 本日はモダンの最新環境のデッキをご紹介していきます! 紹介デッキ ボロスエネルギー エスパー御霊 ネオブランド ボロスエネルギー モダンチャレンジ : 優勝 By rastaf もう当メディアで何度紹介したかわからないデッキ、ボロスエネルギー。 『モダンホライゾン3』生まれ『モダンホライゾン3』育ちのこのデッキは、数々の規制を受けながらも、いまだにメタゲームの最前線をひた走っています。 《オセロットの群れ》《魂の導き手》《敏捷なこそ泥、ラガバン》という環境最高の1マナ域たちから始まり、《ナカティルの最下層民、アジャニ》へと繋ぎ、《ゴブリンの砲撃》が組み合わされば3~4ターンでゲームが決まってしまうスピード。 そして《火の怒りのタイタン、フレージ》《栄光の闘技場》のコンボが中盤以降はちらつくので、決して序盤の猛攻を止めただけではゲームは終わりません。 ボロスエネルギーはビートダウンだと思われがちですが、それは正確ではありません。このデッキは早すぎるミッドレンジです。ミッドレンジが通常使う3~4マナ域の良質なクリーチャーが1~3マナ域になっていることにより、ビートダウンと勘違いされているのです。 ビートダウンなのにカードが強すぎてコントロールもできてしまう、という方が正しいのかもしれませんね。 速すぎる中速デッキ、それがボロスエネルギーを表すのに最も最適な表現でしょう。相手によってゲームレンジを変えられる柔軟性、アドバンテージ力、そしてビートダウン性能。これらを兼ね備えており、とても安定感のあるデッキで、人気なのも納得です。 さて、そんなボロスエネルギーですが、『久遠の終端』から定番になった1枚のクリーチャーがいます。 それが《光に導かれし者、ハリーヤ》です。 終了ステップに3点以上のライフを得ていると1ドローができるこの人間。他のクリーチャーやアーティファクトが出ると1点ゲインするので、《魂の導き手》が戦場にいる時ならば、ワープで《光に導かれし者、ハリーヤ》を出してクリーチャーをもう1体出すだけでカードが引けます。 更に3点はちょうど《火の怒りのタイタン、フレージ》のゲイン量と同じなので、単に《火の怒りのタイタン、フレージ》を出すだけでもドローでき、気軽にアドバンテージが稼げるようになりました。 特にワープコストが1と軽いので、4ターン目にワープで《光に導かれし者、ハリーヤ》+《火の怒りのタイタン、フレージ》は定番の流れ。エネルギーを相手にする際は綺麗にこれを決められないようにしたいですね。 《光に導かれし者、ハリーヤ》は《歴戦の紅蓮術士》とも相性の良いカードです。《歴戦の紅蓮術士》でトークンが2体出るので、ちょうど3点ゲインでカードが引けます。以前は《鏡割りの寓話》などが入っていた3マナ域ですが、最近は《歴戦の紅蓮術士》になっているリストが多いですね。 《鏡割りの寓話》は手札のある状況では《歴戦の紅蓮術士》より強い状況もありますが、手札を枯らした後のトップデッキでは《歴戦の紅蓮術士》は即座に2ドローできるのに対し、《鏡割りの寓話》は手札が増えません。《ゴブリンの砲撃》との相性を考えても《歴戦の紅蓮術士》の方が強力です。 《光に導かれし者、ハリーヤ》の加入によってドローがしやすくなり、以前に比べて中盤戦に強くなりました。《スカルドの決戦》は大量のリソースを稼げるものの、出したターンは4マナを使って何もしないことも多く、メイン戦ではどうしても採用しにくいカードでした。 そのリソースを稼ぐスロットが《光に導かれし者、ハリーヤ》になったので、デッキを重くすることなく中~長期戦に備えられるようになり、デッキとしては純粋な強化と言って良いでしょう。 サイドボードを強く使えるのもボロスエネルギーの強みです。フェア対決で強い一方、コンボには苦戦を強いられるため、《真昼の決闘》《オアリムの詠唱》などなど、白いカードをふんだんに使い、苦手なデッキを対策しています。 メタに合わせて細かいチューンをするだけで大会に持ち込めるのがボロスエネルギーの強さ。いつでも練習する価値のあるデッキです。 エスパー御霊 モダンチャレンジ : 優勝 By _IlNano_ 《偉大なる統一者、アトラクサ》を最速2ターン目に《御霊の復讐》で釣り上げるリアニメイトデッキ、エスパー御霊。 《悲嘆》がいた頃は《悲嘆》+《儚い存在》のコンボを擁するデッキでしたが、《悲嘆》禁止後は実質《偉大なる統一者、アトラクサ》を吊り上げるプランしかなく、モダンでたまに勝つ程度で、さほど活躍していませんでした。 それが『久遠の終端』で《量子の謎かけ屋》が入ったことで大きく変わりました。 《量子の謎かけ屋》をワープして《儚い存在》することで2ドロー、あるいは3ドローできるようになったので、まず《儚い存在》のバリューが上がりました。《悲嘆》という相棒がなくなって以降は《偉大なる統一者、アトラクサ》のためだけに採用していた《儚い存在》に使い道ができたのです。 更に《超能力蛙》との組み合わせです。《超能力蛙》で不要牌を捨てて、《量子の謎かけ屋》を出して2ドロー。この動きが非常に強力で、エスパー御霊は《超能力蛙》+《量子の謎かけ屋》の新たな軸を手に入れました。 このリストは《超能力蛙》のバリューを更に引き出すため、《新たな夜明け、ケトラモーズ》まで採用しています。《超能力蛙》で墓地を3枚追放すると1ドローできるので、相性抜群です。 リアニメイト要素は非常に少なく、4枚の《偉大なる統一者、アトラクサ》と《グリセルブランド》。そして《御霊の復讐》と1枚の《骨の皇帝》のみ。他のカードはすべて除去か妨害、そして《超能力蛙》周りのカードで固められています。 以前は《儚い存在》との相性を考慮して墓地も肥やせる《ファラジの考古学者》が採用されていましたが、《量子の謎かけ屋》が《儚い存在》をより上手く使えるので、《ファラジの考古学者》が抜け、結果的にリアニメイトコンボが決まりづらくなった代わりに、デッキパワーが大幅に上昇しました。 単純なデッキパワーが上がったことで、サイドボード後の戦いも楽になりました。これまでは墓地対策に苦しめられてきましたが、《超能力蛙》《量子の謎かけ屋》《新たな夜明け、ケトラモーズ》のラインが強く、墓地を介さずにゲームに勝てるのです。 相手からするとこのエスパー御霊の並びは非常に厄介です。墓地対策は効きづらいとはいっても、《偉大なる統一者、アトラクサ》を《御霊の復讐》で釣られたらほとんどのゲームで負けてしまうので、墓地対策は用意せざるを得ません。 そんな動きづらい相手を尻目に《超能力蛙》《量子の謎かけ屋》でカードをモリモリと引いていき、7マナで手札から《偉大なる統一者、アトラクサ》を出すなんてことも容易になったのです。《ファラジの考古学者》はスペルしか入らないので、土地が伸びませんでした。その辺りも《量子の謎かけ屋》は克服しているのです。 《量子の謎かけ屋》によってエスパー御霊は間違いなく一つ上のステージに立ちました。現代のエスパー御霊がただ《偉大なる統一者、アトラクサ》を吊り上げるデッキだと思っているならその認識はもう古いですよ! 普段コンボを使わない人も、強固な《超能力蛙》《量子の謎かけ屋》のフェアラインを見れば使いたくなるはず。このデッキは最早、《超能力蛙》デッキに《偉大なる統一者、アトラクサ》《御霊の復讐》のリアニメイトパッケージが入っているだけのフェアデッキかもしれません! ネオブランド モダンショーケース予選 : 優勝 By triosk 先日のモダンショーケース予選で市川 ユウキさんが使用し、見事優勝を収めたネオブランド。このモダンショーケース予選の出場権利を獲得した予選大会でも市川さんはネオブランドを使用しており、ネオブランドマスターですね。 ネオブランドは《新生化》(=ネオ)を打って《グリセルブランド》(=ブランド)を出すデッキなので、そこからネオブランドという名前がついています。 《新生化》はクリーチャーを生け贄にし、それよりマナ総量が1大きいクリーチャーを戦場に出せる呪文。普通に使えばちょっと大きいクリーチャーをデッキから出すだけのサーチ呪文なのですが、マナ総量が大きな軽いクリーチャーを使うことで、《グリセルブランド》をいきなり呼び出せます。 そんな魔法のクリーチャーが《アロサウルス乗り》です。7マナのクリーチャーなのですが、7マナを支払って出したことがある人はほとんどいません。このクリーチャーは0マナです。緑のカードを2枚追放することで0マナで出すことができるのです。 そしてその《アロサウルス乗り》を《新生化》で生け贄にすることで《グリセルブランド》が呼び出せます。2ターン目に《グリセルブランド》を出せてしまうというわけですね。 以前のネオブランドは2ターン目に《グリセルブランド》を出し、そこから14枚のカードを引き、《滋養の群れ》で大量のライフを獲得し、《グリセルブランド》の7枚ドローを続けていき、ライブラリーを引ききって勝利していました。2ターンキルを目指すデッキだったのです。 それは仕方のないことで、キーパーツの《アロサウルス乗り》をサーチするために《召喚士の契約》を4枚入れているため、《アロサウルス乗り》から《グリセルブランド》を出してそのターンに勝てなければ、次のターンの契約コストが払えませんでした。なのでネオブランドはコンボを始めたらそのターンに勝てるように設計されていました。 それが変わったのが『モダンホライゾン3』。青いデッキのサイドカードとして大人気の《記憶への放逐》です。ネオブランドにはこのカードがメインから4枚採用されていますが、これは別にエルドラージ対策ではありません。自分の《召喚士の契約》などの契約コストを踏み倒すのに使います。 契約は次のターンのアップキープにマナの支払いを要求してくるので、それを《記憶への放逐》で打ち消すことで、支払いを踏み倒せるのです。《記憶への放逐》のおかげでネオブランドは、《グリセルブランド》を出してそのターンに勝つ必要がなくなりました。 そのため、《滋養の群れ》《土着のワーム》などコンボ中に必要なだけのカードをデッキから排除することに成功しました。2ターン目に勝つ可能性は低くなりましたが、その代わりに安定して3ターン目に《グリセルブランド》を着地できるようになったのです。 《アロサウルス乗り》は0マナで唱えて《新生化》で《グリセルブランド》を出せる代わりに、手札を追加で2枚消費するデメリットもあります。そこで採用されているのが《わめき騒ぐマンドリル》。 墓地が5枚あれば1マナで唱えられるので、《新生化》と合わせても3マナ。フェッチランドと諜報などを合わせれば3ターン目に墓地を5枚にできるので、7マナのクリーチャーを3ターン目に呼び出せます。そう、《偉大なる統一者、アトラクサ》ですね。ダブルマリガンでリソースが足りなくなった場合はこの《わめき騒ぐマンドリル》から《新生化》を打てるのもポイント。 以前までのネオブランドでは手札が足りなくなることもそれなりにありましたからね。マリガンの多いデッキなのにマリガンできないのもジレンマでした。 《暴走暴君、ガルタ》が入っているのも最近のネオブランドの特徴です。手札に《偉大なる統一者、アトラクサ》や《グリセルブランド》が来て困っている時は、《アロサウルス乗り》で《暴走暴君、ガルタ》を出すことで、手札から一挙に展開できます。以前は《グリセルブランド》が手札に来ると《新生化》でサーチできないため、《グリセルブランドド》を2枚採用していましたが、《暴走暴君、ガルタ》を入れることで1枚に抑えられるようになっています。 ライフが少ない状態では《グリセルブランド》を起動できないという欠点も、《終わらぬ歌、ウレニ》によって克服しています。ボロスエネルギーは《終わらぬ歌、ウレニ》を倒せないため、ほとんどの盤面を1枚で終わらせてくれます。 隙だらけだったネオブランドは気づけば非常に隙の少ないデッキとなりました。理不尽さで言えばアミュレットタイタンを上回るのがネオブランドで、間違いなくモダン最速のコンボです。その理不尽な速度を持つデッキが安定感を手に入れ、より恐ろしくなりました。 今のネオブランドは、モダンを戦う上で間違いなく意識しなければならない相手です!
-

【週刊メタゲーム通信】王者イゼット大釜を脅かすディミーアネズミと赤単アグロ
こんにちは。 細川 侑也(@yuyan_mtg)です。 先週末はチャンピオンズカップファイナルのスペシャル予選に加え、マジックオンライン上で非常に競技性の高いイベント、スタンダードショーケース予選が行われました。 ショーケースチャレンジのトップ8に入賞したプレイヤーと、直前予選で5-0したプレイヤーだけが参加し、優勝者は参加者8人で行われるMOCS本戦に出場でき、同時にプロツアーの権利も獲得できます。 そのため、参加者たちは遊びなしの大本命デッキを持ち込んできます。このショーケース予選は現環境をそのまま反映していると言っても良いレベル! というわけで今回はショーケース予選を中心に、最新メタゲームをお届けします! 紹介デッキ イゼット大釜 ディミーアネズミミッドレンジ 赤単アグロ イゼット大釜 Standard Showcase Qualifier: 2位 By Lillia MTGアリーナ用インポートデータ スタンダードを語る上で欠かせないのがこのイゼット大釜。ローテーション後に大暴れし続け、トップ8に4人は当たり前、6人が入賞するなんて日もあるほど。 テーブルトップ・アリーナ・マジックオンラインとあらゆる環境で勝ちまくっており、当然今回のショーケース予選でも大本命中の大本命。トップ8には4人が進出しています。 デッキのコアパーツである《略奪するアオザメ》《逸失への恐怖》《迷える黒魔道士、ビビ》《アガサの魂の大釜》《冬夜の物語》《プロフトの映像記憶》は初期から変わっていません。 《迷える黒魔道士、ビビ》《アガサの魂の大釜》によるコンボと《プロフトの映像記憶》による攻め、その両方を同時に繰り出し、相手に対応を迫っていく、コンボビートダウンです。 調整ポイントとなっているのはまず《光砕く者、テルサ》《蒸気核の学者》の枠です。 《光砕く者、テルサ》は3/3速攻なので、《プロフトの映像記憶》から3ターン目に出した時の打点が特に魅力です。全体除去にも耐性があるので、対コントロールで優秀ですね。 一方の《蒸気核の学者》は2枚引いてから1枚捨てることで、リソースを稼げるのがまず優秀。そして自身が2/2警戒なので《プロフトの映像記憶》で強化した時に攻防で活躍してくれますし、《逸失への恐怖》で追加戦闘が発生した際に、警戒があるので他のアンタップしたクリーチャーと一緒に殴り続けることができます。 どちらも一長一短ですが、《光砕く者、テルサ》の方がやや優先されており、伝説のリスクもあるので3枚採用で《蒸気核の学者》1枚といったリストが多かったのが初期でしたが、現在ではその枚数はやや拮抗しており、この準優勝したリストでは2枚ずつの採用となっています。 イゼット大釜は基本的に殴るデッキなので《光砕く者、テルサ》の方がデッキと合っているのは確かですが、手札0枚の状況で《光砕く者、テルサ》をトップデッキした際は、ただ出して殴ることしかできません。 一方の《蒸気核の学者》は手札が0枚の時に引いたらとりあえず2ドローできますし、そこで引いたカードによっては手札を残せますし、当然《プロフトの映像記憶》も誘発します。 《光砕く者、テルサ》VS《蒸気核の学者》はこれからも永遠の課題となりそうですが、案外この2枚ずつがちょうどよいバランスなのかもしれませんね。 そして《量子の謎かけ屋》はすっかりイゼット大釜の定番となりました。 手札が1枚以下の時にドローすると追加で1ドローが発生するスフィンクス。手札が枯れやすいこのデッキでは追加のドローは非常に嬉しく、《プロフトの映像記憶》のバリューも跳ね上がります。 それだけでなく、《量子の謎かけ屋》は調和との相性も抜群。ワープで《量子の謎かけ屋》を唱えて、自身をタップすることで《冬夜の物語》を墓地から調和で唱えられるのです。もちろんこの調和の際に手札が1枚以下なら追加のドローも発生し、一気にリソースが爆発します。 《量子の謎かけ屋》が入ったおかげでイゼット大釜はリソース勝負もできるデッキになりました。特にサイド後は墓地対策で《迷える黒魔道士、ビビ》《アガサの魂の大釜》を潰される展開が多く、純粋な《プロフトの映像記憶》ビートになります。 その際はフェアなゲームをする必要があり、《量子の謎かけ屋》は更に活躍してくれるのです。サイド後に真価を発揮するカードですが、そもそもメインに入れても強力だったことが判明したため、最近では多くのデッキにメインから採用されています。 イゼット大釜は固定パーツ以外のチューニングを柔軟に行えるのも強みです。ドローも多くそれらを引き込めるため、カウンターを少し多めにすればコントロールに強くなり、除去を増やせばアグロ耐性が上がります。 スタンダードの王者はまだまだ玉座を譲りそうにはありません。 ディミーアネズミミッドレンジ Standard Showcase Qualifier: 優勝 By Zompatanfo MTGアリーナ用インポートデータ そんなイゼット大釜ばかりのスタンダードショーケース予選を見事優勝したのはディミーアミッドレンジ! 『ダスクモーン:戦慄の館』で今の形が完成してからというもの、ずっとスタンダードで生き残り続けていたデッキが、イゼット大釜を下して見事優勝しました。 ディミーアミッドレンジはトップ8の人数こそイゼット大釜より少ないものの、不思議と優勝回数は多く、単純なトーナメント優勝数だけで見ればディミーアとイゼットは同じぐらいかもしれません。 そしてその注目のリストは、ディミーア・ネズミ・ミッドレンジと名付けられています。そう、このディミーアは通常のリストに比べてネズミ要素が多いのです。 まず2マナ域の定番だった《大洞窟のコウモリ》の枠に入っているのがネズミ、《群青の獣縛り》です。 パワーが2以上のクリーチャーにブロックされない能力で、《悪夢滅ぼし、魁渡》の忍術を達成しやすかったり、《永劫の好奇心》でカードを引く際に便利。攻撃面において優秀なのはもちろん、1/3警戒というスタッツで守りにも貢献してくれます。 クリーチャーやアーティファクトの能力を失わせるので、《アガサの魂の大釜》の起動を防いだり、戦場の《迷える黒魔道士、ビビ》の能力を失わせることも可能です。 《大洞窟のコウモリ》は優秀な手札破壊兼クロックですが、環境の多くのデッキが除去を採用している状況では、ただ相手の手札を見るだけのカードになってしまいます。除去の薄いデッキやコンボデッキが台頭しているなら価値がありますが、イゼット大釜が中心のメタゲームでは除去が飛び交うことは必至。 それなら出してただ除去されるだけの《大洞窟のコウモリ》の意味は薄く、《群青の獣縛り》のように戦闘において優秀なカードを採用したのでしょう。 そしてもう1種のネズミが《下水王、駆け抜け侯》。墓地をけん制しながらネズミを追放し、どんどんクロックを増やしていきます。 《冬夜の物語》や《迷える黒魔道士、ビビ》を追放していくことで相手のコンボを防ぎ、更にクロックも生み出す優秀なクリーチャーです。《永劫の好奇心》が4枚入ったディミーアでは、クリーチャーがとても重要です。除去で何も残らない《分派の説教者》ではなく、とりあえず出したターンに効果のある《下水王、駆け抜け侯》を優先するのも納得です。 このリストはかなりマナカーブが軽くなっています。厚くなりがちな3マナ域を僅か7枚におさえ、序盤からの攻めを徹底しています。1ターン目からテンポよく展開していくことで、《悪夢滅ぼし、魁渡》《永劫の好奇心》は強くなっていきます。 1マナ域が多いことから《始まりの町》を4枚採用しているのもポイント。ディミーアミッドレンジで《始まりの町》4枚のリストは今までに見たことがなかったので驚きましたが、このデッキのコンセプトを考えればその選択も納得です。 サイドボードにはネズミを活かせる《情け知らずのヴレン》も採用しており、このデッキはまさしくディミーアネズミ! イゼット大釜に強いデッキとして注目されており、実績もそれを証明しています。デッキに迷っている方はぜひ試してみるべきですね。 赤単アグロ チャンピオンズカップシーズン4ラウンド2スペシャル予選in吉祥 : 権利獲得 By Hitomi Masaaki MTGアリーナ用インポートデータ イゼット大釜キラーとして先週末に武勲をあげたのは、ディミーアミッドレンジだけではありません。 先週の土曜日の予選で権利を獲得し、その後日本で大流行したイゼット大釜をメタりメタった赤単、それがこちらです。 《剃刀族の棘頭》はイゼット大釜キラーと呼ぶべきカード。対戦相手がカードを引くたびに1点喰らうので、《蒸気核の学者》や《光砕く者、テルサ》は出しにくく、《プロフトの映像記憶》《逸失への恐怖》も1点を受けることになります。 イゼット大釜にとって絶対に除去しなければならないクリーチャーで、序盤に他のクリーチャーに除去を使わされてから出てくる《剃刀族の棘頭》は死を意味します。 《剃刀族の棘頭》の代わりに抜けた2マナ域はなんと《多様な鼠》ですが、考えてみれば《多様な鼠》で対象に取れるクリーチャーは最早《熾火心の挑戦者》と《魂石の聖域》しかありません。1ターン目の《心火の英雄》から《多様な鼠》の流れがなくなった今、このカードは不要と判断したのでしょう。トランプルをつける《巨怪の怒り》が禁止されたのも要因の1つですね。 《焼き切る非行士》もあまり見ることのない珍しいクリーチャー。1マナ1/1威迫でダメージを通しやすく、ひとたび最高速度に達すれば二段攻撃と、1マナ域とは思えない性能です。 1ターン目に引いてよし、2枚目以降を中盤に引いてもそこそこの活躍をしてくれるため、ジェネリック《心火の英雄》と言ったところでしょうか。1マナ域は欲しいけど、弱い1マナ域はいらない。そんな悩みに応えてくれるカードです。 除去の選択も実に独特で、《噴出の稲妻》のキッカーを含めるとすべて4点以上の火力呪文になっています。ディミーアミッドレンジの《分派の説教者》はもちろん、《プロフトの映像記憶》で大きくなった《逸失への恐怖》《光砕く者、テルサ》など、3点では処理できない状況が多発することから、4点以上の除去が多く採用されているのでしょう。 火力を本体に打って勝利する展開はほとんどないため、クリーチャーを出して除去でブロッカーを退けてライフを削ることをまっすぐ目指しています。除去の選択も素晴らしいですね。 日曜日の日本の多くの大会ではこの赤単が活躍し、イゼット大釜を完全に駆逐しており、対イゼット大釜に対する回答として巷で話題沸騰中です。 《剃刀族の棘頭》はドラゴン型の赤単にも採用されはじめ、いよいよイゼット大釜は攻略され始めたと言って良いでしょう。 イゼット大釜・ディミーアミッドレンジ・赤単アグロ。スタンダードの新たな三強がはっきりしたところで、今週はどのようなメタゲームになるのか。そして新たなデッキは現れるのか。 今週もスタンダードから目が離せません。
PICK UP
注目の記事
-

【今週のピックアップデッキ】アゾリウスブリンク/ボロス召集/ティムールスケープシフト
こんにちは。 細川 侑也(@yuyan_mtg)です。 今週のピックアップデッキでは、ちょっと珍しいデッキを、軽い解説を交えて紹介していきます。 紹介デッキ アゾリウスブリンク ボロス召集 ティムールスケープシフト アゾリウスブリンク スタンダードリーグ : 5-0 By DB_Dykman MTGアリーナ用インポートデータ クリーチャーを一時的に追放して、「戦場に出た時」の能力を何度も使い回す。この戦略を主体とするデッキの総称は、《一瞬の瞬き》の英語名にちなんでブリンクと呼ばれています。 初代《一瞬の瞬き》はフラッシュバック付きの優秀なブリンクで、《裂け目翼の雲間を泳ぐもの》や《造物の学者、ヴェンセール》で相手の土地を戻し続けたり、《目覚ましヒバリ》をブリンクさせて一気に2体リアニメイトし、スタンダードで大活躍していました。 最近ではモダンでブリンク内蔵クリーチャー《溌剌の牧羊犬、フィリア》で《ベイルマークの大主》を明滅させるオルゾフブリンクが躍動していますね。 そんな歴史あるアーキタイプ、ブリンクがスタンダードに帰ってきました! まずは肝心のブリンクカードから紹介していきましょう。 いつの間にか採録されていた《魅力的な王子》はブリンク以外にライフゲインと占術を持つ便利なクリーチャー。自身がブリンクカードでありながら、ブリンクを受ける対象としても使えるのが嬉しい。 《忠実な馬、フォーチュン》は騎乗したクリーチャーと自身の2つをブリンクできる乗騎。戦場に出た時に占術2のオマケがあるので、ドローの質を高めながら横のクリーチャーを使い回せます。 『久遠の終端』から入った新しいブリンククリーチャーが《万物の定めを追う者》。戦場を離れるまでクリーチャーを追放するのですが、ワープで唱えるとターン終了時に《万物の定めを追う者》が戦場を離れるので、実質ブリンクです。通常キャストした際は除去としても機能してくれます。さすが暗殺者。 そしてブリンクスペルは《水飛沫の門》!1マナですがソーサリーとそこそこのデメリット。しかし、鳥か蛙かカワウソかネズミをブリンクさせていた場合は1ドローできます。このデッキには1種だけ蛙クリーチャーがいるので、ただの1マナブリンクでない時もあります。 その蛙が《陰気な港魔道士》。他のクリーチャーが死亡せずに戦場を離れていたら1ドローできる蛙で、ブリンクとの相性が最高です。クリーチャーをブリンクするたびに1ドローですからね。《忠実な馬、フォーチュン》などで2体同時に戦場を離れた場合は1ドローしかできませんが、それでも十分。 2マナを支払うと自分のクリーチャーを手札に戻せるので、1ドローしながらそのクリーチャーを戦場に出して再利用できます。 さあ、充実したブリンク陣を見てもらった後は、ブリンク対象となるクリーチャーを見てみましょう。 まずは《量子の謎かけ屋》!今やスタンダードのみならずモダンでも第一線で活躍するスフィンクスですが、戦場に出た時に1ドローできるので、当然ブリンク対象です。手札がなければブリンクで1ドローが2ドローになり……あっという間に手札が回復していきます。 そしてこちらは戦場に出た時ではなく、離れた時に誘発する《反因果の残留》。戦場を離れた時にカードを引いて、その後にコントロールしている土地の数以下のマナ総量のパーマネントをタップ状態で出せます。土地を伸ばして良し、クリーチャーを叩きつけても良しの良質なエルドラージ。 本来はワープで能力が誘発し、その後は死亡時にもう1度誘発する程度のエルドラージなのですが、ブリンクで何度も能力を使い回せるので、このデッキでは一度戦場に出して放置すると大変なことになります。 更に《量子の謎かけ屋》と《反因果の残留》はいずれもワープを持つクリーチャーなので、ブリンクとの相性はぴったりです。ワープはエンド時に追放される代わりに本来よりかなり軽いコストに設定されています。なので、ワープ状態のクリーチャーをブリンクしてそのまま場に定着させる行為は、実質的な踏み倒しとなるのです。 3ターン目に《忠実な馬、フォーチュン》、4ターン目に《反因果の残留》をワープで出して《忠実な馬、フォーチュン》に騎乗して攻撃すると、《反因果の残留》が誘発しながらパーマネントを展開し、最終的に《反因果の残留》が戦場に降り立つことになります。 同じワープ持ちの《星原の歌手》は、戦場に出た時の誘発を倍にします。《魅力的な王子》で4点ゲインしたり、同時に2体をブリンクしたり、《量子の謎かけ屋》で2枚引いたりと、やはり放置すれば大暴れ。《反因果の残留》とは何のシナジーもありませんが贅沢は言えません。 一度動き出すとアドバンテージが止まらなくなるのがブリンクデッキの良いところ。回していてすごく楽しいので、普通のマジックに飽きた方はぜひお試しください。 コスモジャンド パイオニアリーグ : 5-0 By hauterho MTGアリーナ用インポートデータ 小粒なクリーチャーを展開して召集クリーチャーを出して相手をなぎ倒す、横並びビートダウン、ボロス召集。 スタンダードでも活躍したデッキですが、パイオニアの召集は一味違います。 スタンダードではクリーチャーを並べた後の召集カードが《イーオスの遍歴の騎士》でした。クリーチャーを2枚加える強力なカードではありますが、速効性があるわけではありません。 それがパイオニアになると大きく変わります。《イーオスの遍歴の騎士》と同じく、5マナの召集持ちのクリーチャーがもう1種増えるのです。それが《敬慕されるロクソドン》。 しかもその能力は《イーオスの遍歴の騎士》と違い超攻撃的。召集のためにタップしたクリーチャーの上に+1/+1カウンターを1個ずつ置いていくのです。2ターン目に《敬慕されるロクソドン》を出しながら2/2の群れが5体並ぶ恐ろしい場が完成します。 と、ここまでは昔から変わりません。今回なぜボロス召集を紹介したのか?その答えは、『久遠の終端』でとあるカードが入って強化されたからです。 それが《コスモグランドの頂点》! スタンダードでもエスパーピクシーで採用されていたクリーチャー。2回呪文を唱えるとトークンを生成したり、全体強化を行います。このカードがボロス召集と相性が良いことに気が付いたプレイヤーは天才ですね。 まず召集は非常に軽いデッキ。1マナのカードが大半ですし、《羽ばたき飛行機械》に至っては0マナ。3ターン目に《コスモグランドの頂点》を出してそのまま誘発までいけます。 召集クリーチャーたちも場合によっては0マナになるので、やはり3ターン目に《コスモグランドの頂点》を出しながら《イーオスの遍歴の騎士》と繋げて、そこから《コスモグランドの頂点》が誘発します。 そして《コスモグランドの頂点》の能力がどちらも召集と相性が良いのもポイント。横に広げたければトークンを生成すれば良いし、十分にクリーチャーがいるなら全体強化で次のターンの勝利を狙えます。 この3マナのスロットには《イモデーンの徴募兵》が入っていることが多かったと思います。全体強化しつつ速攻を付与するこのカードはフィニッシュの瞬間には効果的ですが、腐る場面もそれなりにありました。クリーチャーが足りなければ中途半端なダメージしか入りません。 しかし、《コスモグランドの頂点》はトークン生成に全体強化と、場面を選ばずに活躍できるカードです。《イーオスの遍歴の騎士》で《コスモグランドの頂点》と1マナクリーチャーをセットで拾われた時の絶望感と言ったらないでしょう。 《ひよっこ捜査員》《スレイベンの検査官》の手がかり8枚体制に《イーオスの遍歴の騎士》なので、《コスモグランドの頂点》は意外と2回以上誘発してくれます。ボロス召集という一撃必殺のデッキが、継続的なトークン生成を手に入れたのはかなりの脅威です。 デッキの性質上、単体除去に非常に強いデッキなので、全除去がメインから大量に入っている環境でなければ、ボロス召集は無双するかもしれません。 《コスモグランドの頂点》の頂点たるゆえん、戦えばわかるはず! ティムールスケープシフト モダンゴールドリーグ : 5-0 By ilGianB1 土地を7枚置いて《風景の変容》を打つと勝利する。モダンにおける《風景の変容》はずっとそんなカードでした。 7枚の土地を生け贄にするとデッキから6枚の《山》と《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》が場に出て、《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》の条件が6枚同時に達成。18点のダメージが飛んで終了。これを《風景の変容》1枚で行えるので、実質スケープシフトは《風景の変容》1枚コンボでした。 《欠片の双子》が《やっかい児》を必要としたり、コンボは基本的には2枚で成立することがほとんど。 その中でたった1枚でゲームに勝利できる《風景の変容》は、人気の土地コンボでした。 しかし現代マジックにおいて、土地をただ7枚並べるという行為は2枚コンボよりもハードルが高い。《風景の変容》と土地7枚を揃えるのは2枚コンボ以上の難易度となってしまい、スケープシフトは現環境からは姿を消しています。 《風景の変容》は《精力の護符》があれば4枚の土地から瞬殺でき、このコンボを擁するアミュレットタイタンは今モダンで最も強いコンボの一つとなっています。2枚コンボに1枚コンボが負けてしまったのです。 《風景の変容》と土地7枚で勝つデッキがモダンで再び脚光を浴びるにはどうすれば良いか?その答えは「速やかに土地を並べる」に他なりません。 そしてそのためのカードが『久遠の終端』で追加されました。その名は《終端探査機》。 1マナ2/2で死亡時にお互いのプレイヤーが着陸船トークンを生成できるというアンコモン。このカードが《風景の変容》に新たな希望を与えました。 着陸船は2マナ起動でライブラリーから基本土地を場に出せるカード。要するに《不屈の自然》を行えるのですが、この着陸船トークンを死亡時に生成するだけの《終端探査機》がなぜ重要なのか? 答えは《耕作の閃光》です。 ライブラリーから基本土地を2枚サーチし、1枚をセットできる3マナのカード。要するに《耕作》なのですが、緑のクリーチャーを生け贄にすることで0マナでキャストできてしまいます。そう、この《耕作の閃光》の生け贄に《終端探査機》はぴったりなのです。 1ターン目に《終端探査機》を出して《耕作の閃光》で生け贄にし、2ターン目に着陸船を起動。これだけで3ターン目に既に5マナが確定するので、1回のマナ加速があればお手軽4ターンキルとなります。 《耕作の閃光》はこれまでもスケープシフトに組み込まれてきましたが、ネックなのは0マナで打つための追加コストでした。緑の軽いクリーチャーは環境にさほど多くなく、マナ加速ができるかもしれない《とぐろ巻きの巫女》やドローできる《氷牙のコアトル》など、不純物となりうるカードを採用せざるを得ませんでした。 その点、《終端探査機》は死亡時に確実に着陸船になるので、まっすぐ《風景の変容》で勝つルートを走ることができます。 《終端探査機》が加わったことで《耕作の閃光》で生け贄にできるクリーチャーが《樹上の草食獣》と合わせて2種となり、1ターン目のキャストがそれなりに安定するようになりました。ようやくモダンで《風景の変容》が《精力の護符》なしでも間に合うようになったのです。 土地を並べて《風景の変容》を打つだけのシンプルなデッキ構成なので、入っているカードも素直なものばかりです。《次元の創世》はマナ加速が必要なら土地を置き、《風景の変容》も探すことができる、まさにこのデッキのためのカード。 《食糧補充》も青いコンボデッキならお馴染みですね。更に土地をたくさん並べるデッキなので、《星間航路の助言》も採用されています。 7枚目の土地を置いて2マナで打ち、7枚の中から《風景の変容》を探してそのまま打って勝つのは美しい流れです。《食糧補充》よりも強い瞬間ですね。 《風景の変容》は4枚しか採用できないため、この手のデッキでは実質《風景の変容》を7枚体制にする《願い》や《白日の下に》などが採用されることがありましたが、ドロースペルが強くなり、《風景の変容》へのアクセスが容易になり、ついにそういった追加の《風景の変容》はすべて抜けました。 《終端探査機》の加入でモダンのスピードに追い付いたティムールスケープシフト!《溶鉄の尖峰、ヴァラクート》を再び噴火させるときが来ました!
-

モダン最新環境をチェック!安定感を増したコンボデッキたちがエネルギーを襲う!
こんにちは。 細川 侑也(@yuyan_mtg)です。 『久遠の終端』は《ピナクルの特使》をはじめ何枚かモダンに影響を与えるカードが登場しましたが、その中でも最もインパクトを残したのは《量子の謎かけ屋》でした。 その後、モダン環境で《量子の謎かけ屋》は生き残っているのでしょうか?そして他の注目のカードたちは使われているのか? 本日はモダンの最新環境のデッキをご紹介していきます! 紹介デッキ ボロスエネルギー エスパー御霊 ネオブランド ボロスエネルギー モダンチャレンジ : 優勝 By rastaf もう当メディアで何度紹介したかわからないデッキ、ボロスエネルギー。 『モダンホライゾン3』生まれ『モダンホライゾン3』育ちのこのデッキは、数々の規制を受けながらも、いまだにメタゲームの最前線をひた走っています。 《オセロットの群れ》《魂の導き手》《敏捷なこそ泥、ラガバン》という環境最高の1マナ域たちから始まり、《ナカティルの最下層民、アジャニ》へと繋ぎ、《ゴブリンの砲撃》が組み合わされば3~4ターンでゲームが決まってしまうスピード。 そして《火の怒りのタイタン、フレージ》《栄光の闘技場》のコンボが中盤以降はちらつくので、決して序盤の猛攻を止めただけではゲームは終わりません。 ボロスエネルギーはビートダウンだと思われがちですが、それは正確ではありません。このデッキは早すぎるミッドレンジです。ミッドレンジが通常使う3~4マナ域の良質なクリーチャーが1~3マナ域になっていることにより、ビートダウンと勘違いされているのです。 ビートダウンなのにカードが強すぎてコントロールもできてしまう、という方が正しいのかもしれませんね。 速すぎる中速デッキ、それがボロスエネルギーを表すのに最も最適な表現でしょう。相手によってゲームレンジを変えられる柔軟性、アドバンテージ力、そしてビートダウン性能。これらを兼ね備えており、とても安定感のあるデッキで、人気なのも納得です。 さて、そんなボロスエネルギーですが、『久遠の終端』から定番になった1枚のクリーチャーがいます。 それが《光に導かれし者、ハリーヤ》です。 終了ステップに3点以上のライフを得ていると1ドローができるこの人間。他のクリーチャーやアーティファクトが出ると1点ゲインするので、《魂の導き手》が戦場にいる時ならば、ワープで《光に導かれし者、ハリーヤ》を出してクリーチャーをもう1体出すだけでカードが引けます。 更に3点はちょうど《火の怒りのタイタン、フレージ》のゲイン量と同じなので、単に《火の怒りのタイタン、フレージ》を出すだけでもドローでき、気軽にアドバンテージが稼げるようになりました。 特にワープコストが1と軽いので、4ターン目にワープで《光に導かれし者、ハリーヤ》+《火の怒りのタイタン、フレージ》は定番の流れ。エネルギーを相手にする際は綺麗にこれを決められないようにしたいですね。 《光に導かれし者、ハリーヤ》は《歴戦の紅蓮術士》とも相性の良いカードです。《歴戦の紅蓮術士》でトークンが2体出るので、ちょうど3点ゲインでカードが引けます。以前は《鏡割りの寓話》などが入っていた3マナ域ですが、最近は《歴戦の紅蓮術士》になっているリストが多いですね。 《鏡割りの寓話》は手札のある状況では《歴戦の紅蓮術士》より強い状況もありますが、手札を枯らした後のトップデッキでは《歴戦の紅蓮術士》は即座に2ドローできるのに対し、《鏡割りの寓話》は手札が増えません。《ゴブリンの砲撃》との相性を考えても《歴戦の紅蓮術士》の方が強力です。 《光に導かれし者、ハリーヤ》の加入によってドローがしやすくなり、以前に比べて中盤戦に強くなりました。《スカルドの決戦》は大量のリソースを稼げるものの、出したターンは4マナを使って何もしないことも多く、メイン戦ではどうしても採用しにくいカードでした。 そのリソースを稼ぐスロットが《光に導かれし者、ハリーヤ》になったので、デッキを重くすることなく中~長期戦に備えられるようになり、デッキとしては純粋な強化と言って良いでしょう。 サイドボードを強く使えるのもボロスエネルギーの強みです。フェア対決で強い一方、コンボには苦戦を強いられるため、《真昼の決闘》《オアリムの詠唱》などなど、白いカードをふんだんに使い、苦手なデッキを対策しています。 メタに合わせて細かいチューンをするだけで大会に持ち込めるのがボロスエネルギーの強さ。いつでも練習する価値のあるデッキです。 エスパー御霊 モダンチャレンジ : 優勝 By _IlNano_ 《偉大なる統一者、アトラクサ》を最速2ターン目に《御霊の復讐》で釣り上げるリアニメイトデッキ、エスパー御霊。 《悲嘆》がいた頃は《悲嘆》+《儚い存在》のコンボを擁するデッキでしたが、《悲嘆》禁止後は実質《偉大なる統一者、アトラクサ》を吊り上げるプランしかなく、モダンでたまに勝つ程度で、さほど活躍していませんでした。 それが『久遠の終端』で《量子の謎かけ屋》が入ったことで大きく変わりました。 《量子の謎かけ屋》をワープして《儚い存在》することで2ドロー、あるいは3ドローできるようになったので、まず《儚い存在》のバリューが上がりました。《悲嘆》という相棒がなくなって以降は《偉大なる統一者、アトラクサ》のためだけに採用していた《儚い存在》に使い道ができたのです。 更に《超能力蛙》との組み合わせです。《超能力蛙》で不要牌を捨てて、《量子の謎かけ屋》を出して2ドロー。この動きが非常に強力で、エスパー御霊は《超能力蛙》+《量子の謎かけ屋》の新たな軸を手に入れました。 このリストは《超能力蛙》のバリューを更に引き出すため、《新たな夜明け、ケトラモーズ》まで採用しています。《超能力蛙》で墓地を3枚追放すると1ドローできるので、相性抜群です。 リアニメイト要素は非常に少なく、4枚の《偉大なる統一者、アトラクサ》と《グリセルブランド》。そして《御霊の復讐》と1枚の《骨の皇帝》のみ。他のカードはすべて除去か妨害、そして《超能力蛙》周りのカードで固められています。 以前は《儚い存在》との相性を考慮して墓地も肥やせる《ファラジの考古学者》が採用されていましたが、《量子の謎かけ屋》が《儚い存在》をより上手く使えるので、《ファラジの考古学者》が抜け、結果的にリアニメイトコンボが決まりづらくなった代わりに、デッキパワーが大幅に上昇しました。 単純なデッキパワーが上がったことで、サイドボード後の戦いも楽になりました。これまでは墓地対策に苦しめられてきましたが、《超能力蛙》《量子の謎かけ屋》《新たな夜明け、ケトラモーズ》のラインが強く、墓地を介さずにゲームに勝てるのです。 相手からするとこのエスパー御霊の並びは非常に厄介です。墓地対策は効きづらいとはいっても、《偉大なる統一者、アトラクサ》を《御霊の復讐》で釣られたらほとんどのゲームで負けてしまうので、墓地対策は用意せざるを得ません。 そんな動きづらい相手を尻目に《超能力蛙》《量子の謎かけ屋》でカードをモリモリと引いていき、7マナで手札から《偉大なる統一者、アトラクサ》を出すなんてことも容易になったのです。《ファラジの考古学者》はスペルしか入らないので、土地が伸びませんでした。その辺りも《量子の謎かけ屋》は克服しているのです。 《量子の謎かけ屋》によってエスパー御霊は間違いなく一つ上のステージに立ちました。現代のエスパー御霊がただ《偉大なる統一者、アトラクサ》を吊り上げるデッキだと思っているならその認識はもう古いですよ! 普段コンボを使わない人も、強固な《超能力蛙》《量子の謎かけ屋》のフェアラインを見れば使いたくなるはず。このデッキは最早、《超能力蛙》デッキに《偉大なる統一者、アトラクサ》《御霊の復讐》のリアニメイトパッケージが入っているだけのフェアデッキかもしれません! ネオブランド モダンショーケース予選 : 優勝 By triosk 先日のモダンショーケース予選で市川 ユウキさんが使用し、見事優勝を収めたネオブランド。このモダンショーケース予選の出場権利を獲得した予選大会でも市川さんはネオブランドを使用しており、ネオブランドマスターですね。 ネオブランドは《新生化》(=ネオ)を打って《グリセルブランド》(=ブランド)を出すデッキなので、そこからネオブランドという名前がついています。 《新生化》はクリーチャーを生け贄にし、それよりマナ総量が1大きいクリーチャーを戦場に出せる呪文。普通に使えばちょっと大きいクリーチャーをデッキから出すだけのサーチ呪文なのですが、マナ総量が大きな軽いクリーチャーを使うことで、《グリセルブランド》をいきなり呼び出せます。 そんな魔法のクリーチャーが《アロサウルス乗り》です。7マナのクリーチャーなのですが、7マナを支払って出したことがある人はほとんどいません。このクリーチャーは0マナです。緑のカードを2枚追放することで0マナで出すことができるのです。 そしてその《アロサウルス乗り》を《新生化》で生け贄にすることで《グリセルブランド》が呼び出せます。2ターン目に《グリセルブランド》を出せてしまうというわけですね。 以前のネオブランドは2ターン目に《グリセルブランド》を出し、そこから14枚のカードを引き、《滋養の群れ》で大量のライフを獲得し、《グリセルブランド》の7枚ドローを続けていき、ライブラリーを引ききって勝利していました。2ターンキルを目指すデッキだったのです。 それは仕方のないことで、キーパーツの《アロサウルス乗り》をサーチするために《召喚士の契約》を4枚入れているため、《アロサウルス乗り》から《グリセルブランド》を出してそのターンに勝てなければ、次のターンの契約コストが払えませんでした。なのでネオブランドはコンボを始めたらそのターンに勝てるように設計されていました。 それが変わったのが『モダンホライゾン3』。青いデッキのサイドカードとして大人気の《記憶への放逐》です。ネオブランドにはこのカードがメインから4枚採用されていますが、これは別にエルドラージ対策ではありません。自分の《召喚士の契約》などの契約コストを踏み倒すのに使います。 契約は次のターンのアップキープにマナの支払いを要求してくるので、それを《記憶への放逐》で打ち消すことで、支払いを踏み倒せるのです。《記憶への放逐》のおかげでネオブランドは、《グリセルブランド》を出してそのターンに勝つ必要がなくなりました。 そのため、《滋養の群れ》《土着のワーム》などコンボ中に必要なだけのカードをデッキから排除することに成功しました。2ターン目に勝つ可能性は低くなりましたが、その代わりに安定して3ターン目に《グリセルブランド》を着地できるようになったのです。 《アロサウルス乗り》は0マナで唱えて《新生化》で《グリセルブランド》を出せる代わりに、手札を追加で2枚消費するデメリットもあります。そこで採用されているのが《わめき騒ぐマンドリル》。 墓地が5枚あれば1マナで唱えられるので、《新生化》と合わせても3マナ。フェッチランドと諜報などを合わせれば3ターン目に墓地を5枚にできるので、7マナのクリーチャーを3ターン目に呼び出せます。そう、《偉大なる統一者、アトラクサ》ですね。ダブルマリガンでリソースが足りなくなった場合はこの《わめき騒ぐマンドリル》から《新生化》を打てるのもポイント。 以前までのネオブランドでは手札が足りなくなることもそれなりにありましたからね。マリガンの多いデッキなのにマリガンできないのもジレンマでした。 《暴走暴君、ガルタ》が入っているのも最近のネオブランドの特徴です。手札に《偉大なる統一者、アトラクサ》や《グリセルブランド》が来て困っている時は、《アロサウルス乗り》で《暴走暴君、ガルタ》を出すことで、手札から一挙に展開できます。以前は《グリセルブランド》が手札に来ると《新生化》でサーチできないため、《グリセルブランドド》を2枚採用していましたが、《暴走暴君、ガルタ》を入れることで1枚に抑えられるようになっています。 ライフが少ない状態では《グリセルブランド》を起動できないという欠点も、《終わらぬ歌、ウレニ》によって克服しています。ボロスエネルギーは《終わらぬ歌、ウレニ》を倒せないため、ほとんどの盤面を1枚で終わらせてくれます。 隙だらけだったネオブランドは気づけば非常に隙の少ないデッキとなりました。理不尽さで言えばアミュレットタイタンを上回るのがネオブランドで、間違いなくモダン最速のコンボです。その理不尽な速度を持つデッキが安定感を手に入れ、より恐ろしくなりました。 今のネオブランドは、モダンを戦う上で間違いなく意識しなければならない相手です!
-

【週刊メタゲーム通信】王者イゼット大釜を脅かすディミーアネズミと赤単アグロ
こんにちは。 細川 侑也(@yuyan_mtg)です。 先週末はチャンピオンズカップファイナルのスペシャル予選に加え、マジックオンライン上で非常に競技性の高いイベント、スタンダードショーケース予選が行われました。 ショーケースチャレンジのトップ8に入賞したプレイヤーと、直前予選で5-0したプレイヤーだけが参加し、優勝者は参加者8人で行われるMOCS本戦に出場でき、同時にプロツアーの権利も獲得できます。 そのため、参加者たちは遊びなしの大本命デッキを持ち込んできます。このショーケース予選は現環境をそのまま反映していると言っても良いレベル! というわけで今回はショーケース予選を中心に、最新メタゲームをお届けします! 紹介デッキ イゼット大釜 ディミーアネズミミッドレンジ 赤単アグロ イゼット大釜 Standard Showcase Qualifier: 2位 By Lillia MTGアリーナ用インポートデータ スタンダードを語る上で欠かせないのがこのイゼット大釜。ローテーション後に大暴れし続け、トップ8に4人は当たり前、6人が入賞するなんて日もあるほど。 テーブルトップ・アリーナ・マジックオンラインとあらゆる環境で勝ちまくっており、当然今回のショーケース予選でも大本命中の大本命。トップ8には4人が進出しています。 デッキのコアパーツである《略奪するアオザメ》《逸失への恐怖》《迷える黒魔道士、ビビ》《アガサの魂の大釜》《冬夜の物語》《プロフトの映像記憶》は初期から変わっていません。 《迷える黒魔道士、ビビ》《アガサの魂の大釜》によるコンボと《プロフトの映像記憶》による攻め、その両方を同時に繰り出し、相手に対応を迫っていく、コンボビートダウンです。 調整ポイントとなっているのはまず《光砕く者、テルサ》《蒸気核の学者》の枠です。 《光砕く者、テルサ》は3/3速攻なので、《プロフトの映像記憶》から3ターン目に出した時の打点が特に魅力です。全体除去にも耐性があるので、対コントロールで優秀ですね。 一方の《蒸気核の学者》は2枚引いてから1枚捨てることで、リソースを稼げるのがまず優秀。そして自身が2/2警戒なので《プロフトの映像記憶》で強化した時に攻防で活躍してくれますし、《逸失への恐怖》で追加戦闘が発生した際に、警戒があるので他のアンタップしたクリーチャーと一緒に殴り続けることができます。 どちらも一長一短ですが、《光砕く者、テルサ》の方がやや優先されており、伝説のリスクもあるので3枚採用で《蒸気核の学者》1枚といったリストが多かったのが初期でしたが、現在ではその枚数はやや拮抗しており、この準優勝したリストでは2枚ずつの採用となっています。 イゼット大釜は基本的に殴るデッキなので《光砕く者、テルサ》の方がデッキと合っているのは確かですが、手札0枚の状況で《光砕く者、テルサ》をトップデッキした際は、ただ出して殴ることしかできません。 一方の《蒸気核の学者》は手札が0枚の時に引いたらとりあえず2ドローできますし、そこで引いたカードによっては手札を残せますし、当然《プロフトの映像記憶》も誘発します。 《光砕く者、テルサ》VS《蒸気核の学者》はこれからも永遠の課題となりそうですが、案外この2枚ずつがちょうどよいバランスなのかもしれませんね。 そして《量子の謎かけ屋》はすっかりイゼット大釜の定番となりました。 手札が1枚以下の時にドローすると追加で1ドローが発生するスフィンクス。手札が枯れやすいこのデッキでは追加のドローは非常に嬉しく、《プロフトの映像記憶》のバリューも跳ね上がります。 それだけでなく、《量子の謎かけ屋》は調和との相性も抜群。ワープで《量子の謎かけ屋》を唱えて、自身をタップすることで《冬夜の物語》を墓地から調和で唱えられるのです。もちろんこの調和の際に手札が1枚以下なら追加のドローも発生し、一気にリソースが爆発します。 《量子の謎かけ屋》が入ったおかげでイゼット大釜はリソース勝負もできるデッキになりました。特にサイド後は墓地対策で《迷える黒魔道士、ビビ》《アガサの魂の大釜》を潰される展開が多く、純粋な《プロフトの映像記憶》ビートになります。 その際はフェアなゲームをする必要があり、《量子の謎かけ屋》は更に活躍してくれるのです。サイド後に真価を発揮するカードですが、そもそもメインに入れても強力だったことが判明したため、最近では多くのデッキにメインから採用されています。 イゼット大釜は固定パーツ以外のチューニングを柔軟に行えるのも強みです。ドローも多くそれらを引き込めるため、カウンターを少し多めにすればコントロールに強くなり、除去を増やせばアグロ耐性が上がります。 スタンダードの王者はまだまだ玉座を譲りそうにはありません。 ディミーアネズミミッドレンジ Standard Showcase Qualifier: 優勝 By Zompatanfo MTGアリーナ用インポートデータ そんなイゼット大釜ばかりのスタンダードショーケース予選を見事優勝したのはディミーアミッドレンジ! 『ダスクモーン:戦慄の館』で今の形が完成してからというもの、ずっとスタンダードで生き残り続けていたデッキが、イゼット大釜を下して見事優勝しました。 ディミーアミッドレンジはトップ8の人数こそイゼット大釜より少ないものの、不思議と優勝回数は多く、単純なトーナメント優勝数だけで見ればディミーアとイゼットは同じぐらいかもしれません。 そしてその注目のリストは、ディミーア・ネズミ・ミッドレンジと名付けられています。そう、このディミーアは通常のリストに比べてネズミ要素が多いのです。 まず2マナ域の定番だった《大洞窟のコウモリ》の枠に入っているのがネズミ、《群青の獣縛り》です。 パワーが2以上のクリーチャーにブロックされない能力で、《悪夢滅ぼし、魁渡》の忍術を達成しやすかったり、《永劫の好奇心》でカードを引く際に便利。攻撃面において優秀なのはもちろん、1/3警戒というスタッツで守りにも貢献してくれます。 クリーチャーやアーティファクトの能力を失わせるので、《アガサの魂の大釜》の起動を防いだり、戦場の《迷える黒魔道士、ビビ》の能力を失わせることも可能です。 《大洞窟のコウモリ》は優秀な手札破壊兼クロックですが、環境の多くのデッキが除去を採用している状況では、ただ相手の手札を見るだけのカードになってしまいます。除去の薄いデッキやコンボデッキが台頭しているなら価値がありますが、イゼット大釜が中心のメタゲームでは除去が飛び交うことは必至。 それなら出してただ除去されるだけの《大洞窟のコウモリ》の意味は薄く、《群青の獣縛り》のように戦闘において優秀なカードを採用したのでしょう。 そしてもう1種のネズミが《下水王、駆け抜け侯》。墓地をけん制しながらネズミを追放し、どんどんクロックを増やしていきます。 《冬夜の物語》や《迷える黒魔道士、ビビ》を追放していくことで相手のコンボを防ぎ、更にクロックも生み出す優秀なクリーチャーです。《永劫の好奇心》が4枚入ったディミーアでは、クリーチャーがとても重要です。除去で何も残らない《分派の説教者》ではなく、とりあえず出したターンに効果のある《下水王、駆け抜け侯》を優先するのも納得です。 このリストはかなりマナカーブが軽くなっています。厚くなりがちな3マナ域を僅か7枚におさえ、序盤からの攻めを徹底しています。1ターン目からテンポよく展開していくことで、《悪夢滅ぼし、魁渡》《永劫の好奇心》は強くなっていきます。 1マナ域が多いことから《始まりの町》を4枚採用しているのもポイント。ディミーアミッドレンジで《始まりの町》4枚のリストは今までに見たことがなかったので驚きましたが、このデッキのコンセプトを考えればその選択も納得です。 サイドボードにはネズミを活かせる《情け知らずのヴレン》も採用しており、このデッキはまさしくディミーアネズミ! イゼット大釜に強いデッキとして注目されており、実績もそれを証明しています。デッキに迷っている方はぜひ試してみるべきですね。 赤単アグロ チャンピオンズカップシーズン4ラウンド2スペシャル予選in吉祥 : 権利獲得 By Hitomi Masaaki MTGアリーナ用インポートデータ イゼット大釜キラーとして先週末に武勲をあげたのは、ディミーアミッドレンジだけではありません。 先週の土曜日の予選で権利を獲得し、その後日本で大流行したイゼット大釜をメタりメタった赤単、それがこちらです。 《剃刀族の棘頭》はイゼット大釜キラーと呼ぶべきカード。対戦相手がカードを引くたびに1点喰らうので、《蒸気核の学者》や《光砕く者、テルサ》は出しにくく、《プロフトの映像記憶》《逸失への恐怖》も1点を受けることになります。 イゼット大釜にとって絶対に除去しなければならないクリーチャーで、序盤に他のクリーチャーに除去を使わされてから出てくる《剃刀族の棘頭》は死を意味します。 《剃刀族の棘頭》の代わりに抜けた2マナ域はなんと《多様な鼠》ですが、考えてみれば《多様な鼠》で対象に取れるクリーチャーは最早《熾火心の挑戦者》と《魂石の聖域》しかありません。1ターン目の《心火の英雄》から《多様な鼠》の流れがなくなった今、このカードは不要と判断したのでしょう。トランプルをつける《巨怪の怒り》が禁止されたのも要因の1つですね。 《焼き切る非行士》もあまり見ることのない珍しいクリーチャー。1マナ1/1威迫でダメージを通しやすく、ひとたび最高速度に達すれば二段攻撃と、1マナ域とは思えない性能です。 1ターン目に引いてよし、2枚目以降を中盤に引いてもそこそこの活躍をしてくれるため、ジェネリック《心火の英雄》と言ったところでしょうか。1マナ域は欲しいけど、弱い1マナ域はいらない。そんな悩みに応えてくれるカードです。 除去の選択も実に独特で、《噴出の稲妻》のキッカーを含めるとすべて4点以上の火力呪文になっています。ディミーアミッドレンジの《分派の説教者》はもちろん、《プロフトの映像記憶》で大きくなった《逸失への恐怖》《光砕く者、テルサ》など、3点では処理できない状況が多発することから、4点以上の除去が多く採用されているのでしょう。 火力を本体に打って勝利する展開はほとんどないため、クリーチャーを出して除去でブロッカーを退けてライフを削ることをまっすぐ目指しています。除去の選択も素晴らしいですね。 日曜日の日本の多くの大会ではこの赤単が活躍し、イゼット大釜を完全に駆逐しており、対イゼット大釜に対する回答として巷で話題沸騰中です。 《剃刀族の棘頭》はドラゴン型の赤単にも採用されはじめ、いよいよイゼット大釜は攻略され始めたと言って良いでしょう。 イゼット大釜・ディミーアミッドレンジ・赤単アグロ。スタンダードの新たな三強がはっきりしたところで、今週はどのようなメタゲームになるのか。そして新たなデッキは現れるのか。 今週もスタンダードから目が離せません。
-

【今週のピックアップデッキ】4色ティーチングコントロール/コスモジャンド/白トロン
こんにちは。 細川 侑也(@yuyan_mtg)です。 今週のピックアップデッキでは、ちょっと珍しいデッキを、軽い解説を交えて紹介していきます。 紹介デッキ 4色ティーチングコントロール コスモジャンド 白トロン 4色ティーチングコントロール スタンダードリーグ : 5-0 By Manuel_Danninger MTGアリーナ用インポートデータ 《神秘の指導》というカードをご存じでしょうか? 『時のらせん』で登場した4マナのサーチ呪文で、インスタントか瞬速を持つカードをサーチすることができるカードです。 当時はこの《神秘の指導》を主軸に据えたティーチングコントロールが『時のらせん』限定構築の環境を席巻していました。 《神秘の指導》で除去かカウンターを拾い、それを使いながら、フラッシュバックで《神秘の指導》をサーチ。《神秘の指導》を1枚引くだけでこれを4回行えるので、非常に再現性の高いコントロールデッキでした。 そんな《神秘の指導》は実は『ファウンデーションズ』で再録されており、スタンダードで使用することができます。そう、ティーチングコントロールがスタンダードに帰ってきたのです! とはいえ、その枚数は控えめで2枚となっています。今のスタンダードには《神秘の指導》を超えるドロースペルがありますからね。 そう、《星間航路の助言》です。2ターン目に除去を探すために打ったり、ゲーム後半ではキッカーで唱えて10枚以上の中から2枚を探すなど、状況に応じて打ち方を変えられる素晴らしい呪文です。 《失せろ》や《稲妻のらせん》など優秀な単体除去や、《喝破》《三歩先》といった強力な打ち消し呪文で低マナ域は構成されており、コントロール好きなら大満足のラインナップです。 ここまでの顔ぶれはジェスカイですが、このデッキは《神秘の指導》のフラッシュバックのために黒を入れています。それなら黒を使わないともったいないですよね。そこで採用されているのが《不可避の敗北》です。 土地以外のパーマネントを追放し、更に3点ドレインのオマケまでついている4マナのインスタント。さすが3色を使う除去なだけあって破格の性能ですが、色が悪くてこれまでは使われることはありませんでした。 3点ゲインはコントロールには非常に嬉しく、プレイし続けるだけで勝手にこちらが有利になるすごい除去です。世が世なら《包囲サイ》クラスの活躍をしていたかもしれません。それぐらいのポテンシャルを秘めています。 当然このカードも《神秘の指導》で探すことができます。 そして《神秘の指導》で引っ張ってこれる必殺技枠は《ジェスカイの啓示》!ジェスカイの根本原理と言われるほど能力を詰め込んだこのカードもインスタント。しかも本体に飛ばすことができるので、たとえ話でもなんでもなく、除去を打ってるだけで勝手に勝ってしまうのがこのデッキなのです。 《稲妻のらせん》含めて除去の多くにはゲインがついており、ビートダウンに対しては高い耐性を持っています。コントロールにも《神秘の指導》のアドバンテージ量で勝つことができ、理論上は最強のデッキかもしれません。 コントロールフリークの皆様はぜひお試しください。 コスモジャンド パイオニアリーグ : 5-0 By xfile MTGアリーナ用インポートデータ ジャンドカラーと言えば、赤緑黒で構成されたミッドレンジ。ミッドレンジとは除去と質の高いクリーチャーで守る中速のデッキで、その中でも手札破壊を使う黒、質の高いクリーチャーの緑、攻めと守りを兼ね備えたアドバンテージ源《血編み髪のエルフ》を使うジャンドカラーがスタンダードでは定番でした。 このミッドレンジ戦略は大流行し、下環境でも猛威を振るいました。軽いカードだけで構成された中速デッキは序盤からアグロには隙がなく、コントロールにも手札破壊とクリーチャーによるビートダウンで勝つことができ、サイドボード後は不要なカードが有効牌に変わることから、不利マッチがとても少ないデッキとなり、モダンでもジャンドは親しまれていました。 モダンでは《稲妻》《思考囲い》《タルモゴイフ》によってジャンドは成立していました。質の高い除去・手札破壊・クリーチャー。ミッドレンジに必要なものはそれだけです。 そしてパイオニアでもミッドレンジは最強であり続けました。ミッドレンジを1枚で体現したカード《鏡割りの寓話》と最強の手札破壊《思考囲い》、そして環境屈指の除去である《致命的な一押し》を使うラクドスミッドレンジです。そんなラクドスに今回久しぶりに緑が加わりました。 その緑のカードとは『久遠の終端』で注目されていた1枚、《コスモゴイフ》!まさかミッドレンジにゴイフが戻ってくる日が来るとは。懐かしさに目頭が熱くなります。 《コスモゴイフ》は《タルモゴイフ》とは真逆で、墓地ではなく追放領域を参照します。自分がオーナーの追放領域にあるカードの数だけパワーとタフネスが上がるゴイフなので、普通に使うだけではただの2マナ0/1です。 しかしご安心してください。このデッキには実にたくさんの追放手段があります。 まずは《墓地の侵入者》。戦場に出た時と殴るたびにどんどん追放領域にカードを溜めていけます。相手の墓地を追放しても無意味なのは少し残念ポイント。 一方《黄金牙、タシグル》は探査を持つ4/5クリーチャー。かつてはミッドレンジの多くに採用されていたカードですが、今回は探査によって追放領域にカードを送り込めることから再注目されました。1マナで出せば5枚を追放できるので、《コスモゴイフ》は一瞬で5/6に膨れ上がります。 そしてなんといっても《悪魔の取り引き》! ライブラリーの上13枚のカードを追放し、その後好きなカードを手札に加えられる。ちょっと変わったサーチ呪文です。先にライブラリーを13枚を追放するので、コンボデッキで使う場合は少しリスクがあるというデザインになっています。 なんとこのカードを打った瞬間に《コスモゴイフ》は13/14と宇宙のようなサイズに!《悪魔の取り引き》でそのまま《コスモゴイフ》をサーチしても良いですし、《コスモゴイフ》が既に殴れているのなら、瞬殺カードを持ってこれます。 それが《ティムールの激闘》。クリーチャーに二段攻撃とトランプルを付与してくれるので、《コスモゴイフ》が突然13/14二段攻撃トランプルとなって相手に襲い掛かるのです! コンボ時以外は腐りがちな《ティムールの激闘》をデッキに入れることができるのは《悪魔の取り引き》のおかげです。強力なサーチ呪文によってこのプランが成立しています。 それ以外のカードはミッドレンジ然とした除去と手札破壊でまとまっており、《コスモゴイフ》も攻防で活躍するクリーチャーなので、《ティムールの激闘》が入っているとはいえ、戦い方はミッドレンジそのものです。 ミッドレンジが好きな方もコンボ好きにもオススメのコスモジャンド、お試しあれ。 白トロン モダンリーグ : 5-0 By kenon 《ウルザの塔》《ウルザの鉱山》《ウルザの魔力炉》。3種の土地を揃えることで7マナ出るぶっとんだ土地。 これらの土地を揃えて大量のマナを出すデッキ、通称ウルザトロン。《森の占術》がスタンダードにやってきた『ミラディン』で一気に人気が爆発し、《歯と爪》を打つ緑トロンから、ドローでトロンを揃えて大量のマナでコントロールする青トロンなど、様々なトロンがスタンダードから下フォーマットまで誕生しました。 モダンでも緑トロンや無色トロンが今も現役で活躍していますが、今回紹介するのはそんなトロン業界に殴り込みにやってきた新たな色。 それが白トロンです! さあ白いトロン、君は何をやってくれるんだ?早速見てみると、他のトロンにはないメリットがありますね。 そう、単体除去です。青トロンも無色トロンもクリーチャーを除去するのがとにかく苦手で、《コジレックの命令》に頼っていましたが、白トロンなら《孤独》を4枚採用できます。 《冥途灯りの行進》は1~2ターン目から打てる除去で、トロンが苦手とする序盤をしっかりと制してくれます。 全体除去も白ならお手の物。万能除去である《神の怒り》に加えて《空の怒り》も入っています。エネルギーを溜めて《空の怒り》を2マナで打つのが本来の使い方ですが、このデッキでは大量のマナを支払って《空の怒り》を大きく唱えます。たくさんのマナを出せるトロンならではの荒業ですね。 白いトロンはドローが不足してしまいがち。《一つの指輪》を失ってかなり心配ではあるものの、ラインナップを見てみるとそれが杞憂であることがわかります。 《大いなる創造者、カーン》はサイドボードの好きなカードにアクセスできる万能カード。「サイドボードの数だけ忠誠値があるようなもの」と言われていますがまさにその通り。除去から墓地対策、《三なる宝球》などの妨害カードまでなんでも揃っています。 そして《嵐の目、ウギン》もドローできるプレインズウォーカー。除去も兼ねており、このカードの存在は、リソースが枯れやすい白トロンにとっては本当に大きいはず。オルゾフなど一部のデッキには《嵐の目、ウギン》を出しただけでもゲームに勝ててしまうでしょう。 《コジレックの命令》《嵐の目、ウギン》《大いなる創造者、カーン》の無色3種のおかげで、最早どのカラーのトロンもリソースを稼ぐのは簡単になりましたね。黒トロンが出てきたのも納得です。 白トロンは、トロンが苦手な序盤のカードにアプローチしやすいのが優秀で、しっかり弱点を克服しています。新たな色のトロンを組むなら、まず長所と短所を意識したいですね。トロンは揃った時の爆発力も重要ですが、どう揃えるか、揃わなかった時にどうするかが肝心。 もしかしたら悩みどころをすべて解決する赤トロンが現れたりなんてこともあるのかも?
-

イゼット大釜とディミーアミッドレンジだけじゃない!スタンダードの有力デッキ
こんにちは。 細川 侑也(@yuyan_mtg)です。 スタンダードは相変わらずイゼット大釜が絶好調!どのトーナメントでも常に複数人が入賞し、最強の名を欲しいままにしています。 ディミーアミッドレンジはそんなイゼット大釜に次ぐ二番手で、この2つのデッキを攻略できるかどうかはカギとなっています。 そして今回はこの二強に続いて最近好成績を上げているデッキたちをご紹介していきます。 紹介デッキ ボロスハツカネズミ 赤単ドラゴン ジャンドコーナ ボロスハツカネズミ スタンダードチャレンジ : 3位 By deleon91 MTGアリーナ用インポートデータ 最高の1マナ域である《心火の英雄》と、《多様な鼠》とあわせて20点近いダメージを叩き出していた《巨怪の怒り》。 このキーカードが2種消えてしまったハツカネズミ主体の赤単アグロですが、今はボロスとなって環境に生き残っています。この最強格の2枚を失ってもまだ勝てるのですから、とんでもないオーバーパワーでしたね。 さて、ボロスカラーは実は今のスタンダードで非常に組みやすい2色となっています。《戦場の鍛冶場》が落ちてしまったものの、『久遠の終端』で《聖なる鋳造所》が再録され、これが《サンビロウの境界》のための土地タイプカウントも満たすので、マナベースとしてはむしろ強化されました。 《心火の英雄》を失った1マナ域を埋めるのはその白いカード。《花足の剣豪》は1マナ1/2とスタッツこそ並ですが、新生能力を持っていて、3マナで出すと2体に広がります。 そしてその能力も強烈。自身が呪文や能力の対象になった時に、それが1回目なら、ハツカネズミが+1/+0修正を受けます。つまり《多様な鼠》で二段攻撃を付与すると、ハツカネズミが全体強化されるのです。新生で出した分を含めて2体の《花足の剣豪》が対象になれば全体に+2修正が入り、凄まじい打点を叩き出します。 他の低マナ域にはかつての赤単のエースたちが並んでおり、《雇われ爪》、《熾火心の挑戦者》、《多様な鼠》は腕を組んでいます。《熾火心の挑戦者》と《多様な鼠》が存在する限り、赤いアグロが環境から消えることはないのでしょう。早いクロック、リソース、爆発的な打点、それらをすべて持つのがこのコンビです。 最強の3マナ域、《叫ぶ宿敵》の横にいるのは《岩山炎の後継者、メイブル》。ハツカネズミを全体強化するだけでなく、戦場に出た時に装備品《岩山炎》を生成します。 この装備品は装備クリーチャーに+1/+1、警戒、トランプル、速攻を付与するなかなかの優れもので、伝説ではないため2枚は置けませんが、それでも十分強力。 《岩山炎の後継者、メイブル》自身がロードなため対処しなければならず、倒したとしても装備品によって後続が強くなる、中々厄介なクリーチャーです。そして当然装備品も能力なので、《花足の剣豪》を誘発させてくれます。《岩山炎の後継者、メイブル》と《花足の剣豪》は非常に相性が良いカードです。 4マナ域の《髭谷の先駆け》は初めて見たという方も多いのではないでしょうか? こちらもハツカネズミ。《心火の英雄》たちと同じく雄姿能力を持っており、マナ総量が3以下のクリーチャー・カードをライブラリーの上5枚から戦場に出すことができます。出すクリーチャーはハツカネズミに限らずなんでもOKなので、《叫ぶ宿敵》を呼び出せます。 場に出さない選択もでいるので、全体除去に対して手札に速攻クリーチャーを温存したり、手札に加えて新生で出すことも可能と、ハツカネズミの事情にぴったりなクリーチャーです。低マナ域から高マナ域まで、対処しなければ終わりなクリーチャーが揃っているのがこのボロスハツカネズミ。 白の利点である《幽霊による庇護》も採用しているので対アグロ性能もバッチリ。イゼット大釜ばかりを意識していると、ハツカネズミに蹂躙されることになりますよ。 赤単ドラゴン スタンダードチャレンジ : 6位 By numberonenoob MTGアリーナ用インポートデータ 続いて紹介するのも赤単のアグロデッキ!なのですが、こちらはなんと《熾火心の挑戦者》《多様な鼠》のハツカネズミの力は借りていません。 その代わりにもっと巨大な者たちの力を借りています。 そう、それがドラゴンです。 ドラゴンと言えば思い浮かぶ人間がタルキールには一人いますよね?ええ、ドラゴンを愛する男、サルカンです。《龍へと昇る者、サルカン》はドラゴンデッキで輝く1枚。 戦場に出た時にドラゴンの後見を受けていると宝物を生成し、ドラゴンが戦場に出るたびに強くなり、ターン終了時まで飛行を得る。ドラゴンを出すためのマナを作りながら、ドラゴンが出ると強くなる。《龍へと昇る者、サルカン》はそんなカードです。 発売直後から注目されていたカードではありましたが、ネックだったのはそのドラゴンによって強くなる部分でした。ドラゴンは基本的にどれも重く、《龍へと昇る者、サルカン》が強くなるのが遅かったので、能力を上手く生かせませんでした。 「《龍へと昇る者、サルカン》を出した次のターンに出せる強いドラゴンがあれば」と言われていました。 そんなプレイヤー、そしてサルカンの望みを『久遠の終端』が実は叶えていました。これまで世界のどこにもなかったサルカンとぴったりの相性のドラゴンは宇宙にいたのです。 その名は《新星のヘルカイト》。5マナ4/5飛行、速攻とドラゴンらしいサイズと能力を持ち、戦場に出た時にクリーチャーに1点を与えてくれます。そして《新星のヘルカイト》が持つ能力がワープ。 3マナで戦場に出て速攻で攻撃し、その後5マナで出し直すことができるのが《新星のヘルカイト》。これが《龍へと昇る者、サルカン》と最高の相性だったのです。 2ターン目に《龍へと昇る者、サルカン》を出して《新星のヘルカイト》を公開して宝物を生成。次のターンにワープで《新星のヘルカイト》を唱えて、サルカンが成長して7点。次のターンに宝物を生け贄に《新星のヘルカイト》をプレイすると8点。ワープの次のターンに宝物のおかげで《新星のヘルカイト》を通常キャストできるのです。 もちろんドラゴンが《新星のヘルカイト》だけでは《龍へと昇る者、サルカン》は真価を発揮しませんが、そこは安心。除去である《双つ口の嵐孵り》、そして『ファウンデーションズ』で再録された《雄牛のやっかいもの》のおかげでドラゴンの枚数は合計で10枚になっています。 《双つ口の嵐孵り》と《雄牛のやっかいもの》だけでもドラゴンの数自体は担保できたかもしれませんが、《新星のヘルカイト》がないと《龍へと昇る者、サルカン》を使う気にはならないでしょう。それぐらいこの2枚の相性は抜群です。 今後《黄金架のドラゴン》クラスのカードが出れば《龍へと昇る者、サルカン》は更に価値が上がるでしょうし、《新星のヘルカイト》は《龍へと昇る者、サルカン》と一緒にずっと使われるはず。このコンビには今後も目が離せません。 ジャンドコーナ スタンダードリーグ : 5-0 By bolov0 MTGアリーナ用インポートデータ パーマネントを手札から踏み倒せる、夢がたっぷり詰まったカード、《救助のけだもの、コーナ》。ただしその条件として、パーマネントを出す能力は生存達成時、つまり第二メインフェイズの開始時に、《救助のけだもの、コーナ》がタップ状態で戦場にいなければなりません。 第二メインフェイズにタップ状態であるということは、通常は《救助のけだもの、コーナ》が攻撃し、無事に生き延びて戦闘が終わることを意味します。4ターン目に《救助のけだもの、コーナ》を出したとすると最速で5ターン目。除去もブロックもされずに能力を持たない4/3が生き延びるのはスタンダードではまず不可能です。 そう、普通ならば。 しかし《救助のけだもの、コーナ》の生存を特殊な方法で満たせるなら話は別です。生存の条件は該当クリーチャーがタップ状態であること。何も攻撃だけが生存を達成する方法ではないのです。 まずは搭乗です。機体を動かすためにはクリーチャーを寝かせる必要があり、これで生存達成となります。採用されている機体は《重厚な世界踏破車》。 戦場に出た時と攻撃した時に土地を伸ばせるので、《救助のけだもの、コーナ》で踏み倒すカードを手札から普通に唱えることもできるようになり、とてもデッキと噛み合っています。生存達成する《救助のけだもの、コーナ》を除去すると《重厚な世界踏破車》に殴られ続け、《救助のけだもの、コーナ》を残せば踏み倒されてしまいます。 そして『久遠の終端』で登場した新たな能力、配備。こちらはクリーチャーをタップすることでカウンターが乗り、一定以上の個数が溜まるとすごい起動型能力が使えるというもの。土地枠で《救助のけだもの、コーナ》をタップして生存能力を起動できるようになったのです。 《目覚めの安息地、エヴェンド》はクリーチャー分だけ緑マナを生む《ガイアの揺籃の地》になり、《記念の星、カヴァーロン》は土地を生け贄にロボットを生成し、その後全クリーチャーにパワー修正と速攻を付与します。どちらも単に《救助のけだもの、コーナ》の生存のためだけでなく、条件達成後の能力も非常に強力です。 さて、これで《救助のけだもの、コーナ》の生存が容易であることがわかりました。肝心の踏み倒すカードはというと、《全知》のような一撃必殺カードは採用されていません。 このデッキは《救助のけだもの、コーナ》の生存を意識はしていますが、決して依存していないのが特徴。《重厚な世界踏破車》からのマナ加速だけで出せるようなクリーチャーばかりです。 4枚採用されているのは《宝物庫生まれの暴君》。《不屈の独創力》でもお馴染みの恐竜で、自身やパワー4以上のクリーチャーが戦場に出た時に3点ゲインと1ドロー。更に死亡時にトークンになり帰ってくるので、除去2枚が必要となる上に2ドローで、1枚でとんでもないリソース差をつけてくれます。 デッキで一番重い《恐怖を喰うもの、ヴァルガヴォス》はさすがに手札から出すより《救助のけだもの、コーナ》から踏み倒したいカード。《逃げ場なし》が環境から消え気味な今、この護法は輝きます。 面白いのは《早駆ける業火、カラミティ》。騎乗したクリーチャーのコピーを2体生成する乗騎なのですが、《宝物庫生まれの暴君》との相性は抜群です。 《宝物庫生まれの暴君》で騎乗して《早駆ける業火、カラミティ》が攻撃すると、まず最初に《宝物庫生まれの暴君》トークンが生まれて1ドローとゲイン、そして2体目のトークンが出てきてそれぞれが誘発し、2ドローと6ゲインが入ります。 《峰の恐怖》をコピーすれば瞬殺ですし、大型クリーチャー同士のシナジーがとても気持ち良いデッキです。 《救助のけだもの、コーナ》の他にも踏み倒し手段として《密輸人の驚き》が採用されています。手札からクリーチャーを2体出したり、4枚切削した中からクリーチャーを加えるこのインスタントは、クリーチャーを拾う手段、踏み倒しの両方に使えて便利です。 《幻獣との交わり》を採用しているおかげで切削も活きる可能性があります。墓地からフラッシュバックすると4/4の英雄譚になり、次のターンに緑を2つ生成してくれて、5ターン目に7マナを生み出します。 7マナと言えばもちろんこのデッキのエース、《宝物庫生まれの暴君》。実に様々な手段で《宝物庫生まれの暴君》を出し、そこから暴れるこのデッキは、最早ジャンド暴君と呼ぶべきかもしれませんね。 強さと楽しさを兼ね備えたジャンドコーナ、今後数が増えていきそうな予感がしています。とても良いデッキなのでぜひお試しください。
-

ものまねが無限を引き起こす!統率者:《世界を救うものまね中、ゴゴ》
みなさんこんにちは!ゆうやん(@yuyan_mtg)です。 本日は僕自身初めてとなる統率者の記事になります! 当然僕の愛するヤシュトラ様のデッキ……ではなく。 《世界を救うものまね中、ゴゴ》です!! 友人からこの統率者の存在を教えてもらい、そこから自分で1枚1枚カードを吟味して組み上げ、かなり思い入れのあるデッキになりました。 目次 《世界を救うものまね中、ゴゴ》とは? 無限コンボ デッキリストとカード紹介 マリガン デッキの回し方 妥協リスト 《世界を救うものまね中、ゴゴ》とは? 《世界を救うものまね中、ゴゴ》は、ファイナルファンタジーの通常セットに収録されているカード。とはいえ、スタンダードでは使用された実績はほぼありません。 なので、まだテキストを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか?というわけでゴゴのカードテキストをおさらいしましょう! 自分のコントロールしている起動型能力や誘発型能力をコピーするという、ものまね能力を持つ《世界を救うものまね中、ゴゴ》。2マナで1回コピーし、4マナを支払えば2回コピーできるので、たくさんマナがあればそれだけすごいことが起きます。 起動型能力と言えばまず思いつくのは《一つの指輪》のようなドロー能力や、《世界を救うものまね中、ゴゴ》のようにクリーチャーの起動型能力が主ですが、実際にはフェッチランドの起動をコピーしたり、サイクリングをコピーして大量にカードを引くなど、様々なものがあります。 もうこれだけでワクワクしてきませんか?《世界を救うものまね中、ゴゴ》はもうすごい統率者なのです! ただし、《世界を救うものまね中、ゴゴ》はとても非力なので殴り勝つことは到底無理。無限コンボで勝つデッキなので、ブラケット4以上で遊んでください。 無限コンボ ゴゴ+アンタップ+3マナファクト+サイクリング デッキリストをご紹介する前に、最も基本となる動きについてご紹介しましょう。 必要なのは《世界を救うものまね中、ゴゴ》、パーマネント(クリーチャーとアーティファクト)をアンタップできるカード、タップで3マナを生み出せるアーティファクト、そしてサイクリングできるカードです。 サイクリングカードが手札に、それ以外のカードが戦場にあり、かつ8マナが生み出せる状態であれば、無限ドローできます。 手順は以下です。 1.《砂時計の侍臣》を起動して《世界を救うものまね中、ゴゴ》をアンタップ。その起動型能力を《世界を救うものまね中、ゴゴ》で8マナ使って4回コピーする。 2.アンタップ能力のコピー3回で《玄武岩のモノリス》を3回アンタップ。9マナを生み出す。 3.4回目のアンタップのコピーは《世界を救うものまね中、ゴゴ》を対象にし、これをアンタップ。 4.スタック中にあるアンタップ能力を再び《世界を救うものまね中、ゴゴ》で4回コピー。9マナの内8マナを使ってループできるので、1ループにつき1マナが増えていく。 5.最終的に無限マナになるので、最後に手札からサイクリングを行い、それを《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーすることで、無限ドロー。 と、アンタップ能力を《世界を救うものまね中、ゴゴ》で複数回コピーすることで、最終的に無限ドローになります。 もちろんサイクリングの代わりに《精神石》を使っても無限ドローになりますし、サイクリングの部分は別の手段で構いません。起動型能力でカードが引ければデッキをすべて引ききれます。 3マナ出るマナアーティファクトは、代わりに《睡蓮の原野》でも無限になります。3マナの場合は、3回コピーで9マナになって初めてマナが増えるので、合計で8マナ必要になりますが、《彩色の宇宙儀》は1回で5マナが出るので、2回コピーするだけで無限になります。X=2の計4マナで《彩色の宇宙儀》と《世界を救うものまね中、ゴゴ》をアンタップし続けるだけで無限なのです。 ゴゴ+《時間の大魔道士、テフェリー》 こちらは2枚コンボ。《時間の大魔道士、テフェリー》のマイナス1能力を《世界を救うものまね中、ゴゴ》でX=1でコピーするだけで無限になります。 土地3枚とゴゴをアンタップし、X=1(2マナ)でこのループを繰り返せるため、非常にお手軽な2枚コンボとなっています。 青単だとテフェリーをサーチできないのが残念。 ゴゴ+《止められない計画》+3マナファクト ターン終了時限定の無限マナ。 《止められない計画》で土地以外のパーマネントがアンタップするので、その能力をコピーして無限を生み出します。 最初の基本コンボと違い、《砂時計の侍臣》などのアンタップクリーチャーが必要ないのがメリット。3マナファクトでなくても、土地以外から合計で3マナ出れば無限マナになるのが良いですね。 手順はシンプルで、ターン終了時の《止められない計画》のアンタップ能力をX=1でコピー。《世界を救うものまね中、ゴゴ》とマナファクトが起きるので、それを再びコピーして無限マナです。 ターン終了時の無限マナなので、ここに無限ドローが絡んだとしても、確実に勝利できるとは限りませんが、この時に無色ではなく青マナの無限マナが出ていたら、《青の太陽の頂点》を全員に打ち込んで勝利できます。(マナファクトが《エルドレインの玉座》や《金粉の水蓮》だった場合に可能) 無色マナで無限が発生する場合は妨害をすべて引き込んでエンドすることになりますね。 《一つの指輪》+《精神力》 《世界を救うものまね中、ゴゴ》と一切関係ない無限。《一つの指輪》を起動して、引いたカードを捨てて《精神力》で《一つの指輪》をアンタップすることで、ライブラリーをほとんどすべて引ききることができます。 最終的には《一つの指輪》に乗ったカウンターがライブラリーの枚数を超えてしまうので、全部引ききることはできませんが、数枚を残してすべてを引けるので、そこから別の無限手段に進み、勝利となります。 《鑑識の利器師》+《玄武岩のモノリス》 《鑑識の利器師》はアーティファクトの起動型能力を軽くする能力を持っています。 《玄武岩のモノリス》は3マナで自身をアンタップでき、それが《鑑識の利器師》によって2マナになるので、無限にこれを繰り返すことで無色の無限マナを作れます。 《大変成家、アンクタス》+アンタップするクリーチャー2種 青いクリーチャーがタップ状態になるたびにカードを引いて捨てることができる《大変成家、アンクタス》を利用し、任意の数だけライブラリーを掘り進めることができます。 《命運縫い》や《砂時計の侍臣》など、クリーチャーをアンタップする手段が2枚あれば、《砂時計の侍臣》で《命運縫い》を起こし、《命運縫い》で《砂時計の侍臣》を起こすことで、無限ルーターを引き起こせます。 手札が少なければ《一つの指輪》などを引き込みにいき、手札が潤沢ならそのまま無限パーツを集めにいけばOK。 デッキリストとカード紹介 こちらが今使用しているデッキリストです。役割別にカードを紹介していきます。 アンタップするカード 無限コンボを決める際にアンタップ手段は必須なので、少し弱めでもなるべく採用するようにしています。 基本的にはすべて同じ能力を持っているので、2マナである《アフェットの錬金術師》は優秀。ですが、この中で一番強力なのは《砂時計の侍臣》です。 《砂時計の侍臣》だけクリーチャー以外のアンタップ手段なので、戦場に出てなくても《世界を救うものまね中、ゴゴ》で無限を決められるのです。サイクリングした時のアンタップ能力を《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーできますからね。しかもそのままサイクリングのドローも《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーできるので、《砂時計の侍臣》だけで無限パーツ2枚分になります。 《命運縫い》は墓地から蘇生で戻せるので、突然無限を決められる便利なクリーチャーです。 《ケルピーの道案内》《療病院のヨレス》《鑑識の研究者》はどれも3マナのアンタップ手段で他には特に能力を持たないのですが、《療病院のヨレス》だけは伝説のクリーチャーを2体アンタップできます。 《殺人人形、マーヴィン》と組み合わせることで《療病院のヨレス》+他の伝説のクリーチャーを無限にアンタップできるようになります。《最高工匠卿、ウルザ》《大変成家、アンクタス》と組み合わせることで無限マナを発生させられるようになるのですが、この4枚コンボはめったに揃いません。 打ち消し 青と言えば打ち消しなので基本的なところは大体入っています。《精神壊しの罠》も入れたいのですがスロットが…。 コンボを決めに行くために使ったり、コンボを止めるのに使ったりと用途はいろいろ。 打ち消しの枚数は非常に難しいですね。個人的には10枚が限度で、9枚でも多め。8枚ぐらいがベターには感じています。手札に打ち消しばかり溜まっても困ってしまいますからね。とはいえ突然の即死を止めるには必要な場合もあり難しい。やはり《精神壊しの罠罠》はあった方が良い気もしてきました。 《世界を救うものまね中、ゴゴ》でリソースを取りやすいのでピッチ系カウンターが使いやすいのは嬉しい。 除去 青単の宿命として、除去手段はかなり弱めです。とはいえ《ドラニスの判事》《オークの弓使い》など、処理しなければならないヘイトベアが死ぬほどあるのが統率者戦。青単でできる限りの妨害手段を入れています。 最も強いのは《金粉のドレイク》ですね。統率者をそのままいただいて無効化したり、《オークの弓使い》をパクって美味しい思いができます。 《両生類の豪雨》もかなり強い除去で、同時に複数体のクリーチャーを処理できたり、統率者につけても○。勝手にスペルを撃ち合ったタイミングを狙えばストームも稼げますね。 《サイクロンの裂け目》はゲームを逆転できる全体バウンスで、《朦朧への没入》は土地としても置けるバウンスカード。純粋な単体バウンスは今回採用していません。 《猿術》《急速混成》は《剣を鍬に》だと思って使っています。 ドロー手段 《一つの指輪》はプレミアムなドローカード。あまりに強すぎます。《通電式キー》などで起こすだけで、唱えた瞬間に3ドローが確定しますし、《世界を救うものまね中、ゴゴ》で起動型能力をコピーすると、カウンターが乗ってドローするところまでコピーされるので、実質アンタップして再起動と同じことが起きます。 《一つの指輪》で勝つことが多いため、デッキにはアーティファクトサーチも多く、その影響もあり、純粋なドローカードは少なめ。 《一つの指輪》以外のドロー手段はすべてサイクリング。つまり《世界を救うものまね中、ゴゴ》で無限マナを出した後の勝ち手段として使うカードたちです。サイクリングによる無限ドローの良いところはやはり打ち消されない点ですね。無限マナは許すけど最後に打つスぺルは消されるというケースもあるので、サイクリングによる無限ドローは意外と強力です。 サイクリングカードはたくさんありますが、絶対的な条件は1マナであることです。1~2ターン目にやることがない時はとりあえずサイクリングすることも多いですし、《世界を救うものまね中、ゴゴ》で1回か2回コピーするケースも多く、1マナと2マナでは大きな差があります。 軽さの次に重要なのは無色であるかどうか。マナアーティファクトからサイクリングできるようにするために無色の方が基本強めです。 そしてカード自体の強さです。サイクリング以外の能力がどれぐらい優秀かですね。《魔道士の悪知恵》は通常使いなら最優秀カードで、《世界を救うものまね中、ゴゴ》を守れる便利なサイクリングです。 《検閲》もまずケアされないので割と《対抗呪文》になります。すいません、言い過ぎました。 最初はサイクリングを大量に入れていたのですが、最終的にはこれぐらいの枚数に落ち着きました。サイクリングもタダじゃないですし、所詮ただの1ドローなので、入れすぎると弱かったです。 サーチ このデッキはアーティファクト主体で、インスタント・ソーサリーに重要なカードはないので、《神秘の教示者》は入れていません。そのためサーチは少なめです。 基本的には《一つの指輪》をサーチすることが多く、《冷酷な船長、テゼレット》以外はすべて《一つの指輪》にアクセスできます。とはいえコンボが大体揃っている時はコンボパーツをサーチすることもあり、その辺は場の状況で判断します。 妨害があることも考えると大体の状況で《一つの指輪》が安定なのですが。 《求道者テゼレット》はマイナス能力でサーチできるので《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーできる点も魅力。マイナス4をコピーして《一つの指輪》《巻き戻しの時計》とサーチするのもよくやります。各対戦相手ごとに《一つの指輪》がアンタップするので死ぬほどドローできます。 唯一《一つの指輪》をサーチできない《冷酷な船長、テゼレット》ですが、魅力的なのはその軽さ。3マナなので《玄武岩のモノリスス》などから出すことができ、プラス能力でマナファクトを起こすも良し、マイナスで《太陽の指輪》などにアクセスして次のターンに備えられます。 《歩行バリスタ》をサーチすれば除去も行えるのでとても使いやすい便利なカードです。 マナアーティファクト 3マナ以上出るマナファクトは直接無限コンボに繋がるので、かなり多めに採用しています。 《久遠なる栄光の笏》は単色デッキ限定の《スランの発電機》。通常は1マナしか出ませんが、同じ名前の土地を3枚以上コントロールしていると3マナが出ます。《スランの発電機》と違い青3つが出るので、有色無限マナが生み出せます。前述のように、インスタントタイミングで無限マナを決めた時に使います。 《エルドレインの玉座》《彩色の宇宙儀》は無限マナを生み出しつつ、無限ドローにもなる最高のカードです。 0マナファクトはこの4種のみです。《オパールのモックス》はアーティファクトが大量のこのデッキでは実質《Mox Sapphire》。 《金属モックス》は手札こそ使うものの、ほぼ無条件にマナを増やせるのはやはり強力ですね。入れない理由はないです。 序盤のマナ加速には貢献しませんが、やはり《モックス・アンバー》も強い。《世界を救うものまね中、ゴゴ》を出して《モックス・アンバー》から打ち消しを構えられるのもグッド。 そして《Jeweled Amulet》。1ターン目に出せば2ターン目に《世界を救うものまね中、ゴゴ》を出すことができます。余った時に溜めておけるので割と便利ですね。完全に使い捨ての《水蓮の花びら》より好みです。 《モックス・ダイアモンド》は採用しませんでした。土地を捨ててマナを伸ばす行為にあまりメリットを感じなかったためです。表面が呪文の両面土地を3枚採用していることもあり、土地の総数は少なく、その上フェッチランドは《世界を救うものまね中、ゴゴ》のために温存したい。そうすると土地が余っているシチュエーション自体がさほどなかったのです。 その他のマナファクト。《友なる石》は大体のデッキに入りますが、単色デッキなら《秘儀の印鑑》と変わらないので今回は採用せず。 手札が《一つの指輪》で溢れるので《思考の器》は結構強め。優先度は高いです。 《精神石》は最終的に《世界を救うものまね中、ゴゴ》で無限ドローできるので、無限マナを決めた後の勝ち手段としても使えます。優秀ですね。 《永遠溢れの杯》はX=3以上で置くと3マナファクトになるので、急に無限マナパーツになります。2ターン目に置けばマナ加速ですし、素晴らしいカードですね。《冷酷な船長、テゼレット》で一応サーチしてこれますが、そういう時は大体《魔力の櫃》を持ってきます。 ただのマナ加速とは違うカードたち。いずれも能力を起動するためにしか使えないので、普通のデッキにはなかなか入らないのですが、《世界を救うものまね中、ゴゴ》ではほぼ《太陽の指輪》です。そう、《世界を救うものまね中、ゴゴ》の起動にこのマナを使えるのです。 つまりこのデッキだけ《太陽の指輪》が3枚ということになります!すごい!片方は《お告げの行商人》なのでアーティファクトですらありませんが、細かいことは気にしないでください。 《奇怪な宝石》は勝ち手段も兼ねています。最終的に作製で《歩行バリスタ》を追放しながら変身し、《歩行バリスタ》内蔵の《啓蒙の神座》として全員を破壊してくれます。 インスタントタイミングで動くことを常に意識しつつ、即死を避ける立ち回りを続けてください! 妨害パーマネント 置いておくだけでヘイトが向いてしまうほど強力なパーマネントたち。 《リスティックの研究》は置き得カードですが、《神秘的負荷》はとりあえず置いておけば良いカードではありません。維持するのにマナがかかるので、《神秘的負荷》が置いてある時は動かなければ良いだけですからね。特に1ターン目に置く時はかなり考えましょう コンボを決めるターンやその前のターンなどに置き、動きを制限するのが良いです。重要なパーマネントの展開の際に置いておけば、相手の打ち消しなどでカードを引けますからね。 とはいえ、マナを持て余しているなら、多少早めに置いても良いです。 《冬の月》は単色デッキで使える強力な妨害カード。ほぼ《冬の宝珠》なのに自分はさほど被害を受けないと素晴らしいですね。 《基本に帰れ》も採用候補ですが、現状はスロットがありません。ガチの大会に出るなら入れそう。 フィニッシャー 無限マナの後に無限+1/+1カウンターで出して勝ちます。非常に簡単なフィニッシャー。青単では数少ない除去にもなるクリーチャーで、もし《歩行バリスタ》と同じ能力を持つクリーチャーが3種いるなら3種とも入れたいですね。 最もよくある勝ち手段が《青の太陽の頂点》。全員に無限ドローさせて勝利します。勝ち手段の中で唯一インスタントなので、《止められない計画》中に勝てるのが魅力です。 普段使いも悪くなく、マナが余りがちなこのデッキではX=4程度ではすぐに打てます。《歩行バリスタ》と同じく、勝つ瞬間以外にも貢献してくれるグッドカードです。 カウンターが1000個乗ってる時に対戦相手を全員倒すびっくりどっきりメカ。ネタかと思いきやこれが実は結構強い。 アンタップステップにアンタップした数だけカウンターが乗り、2マナでそのカウンターを倍にできます。この能力を《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーできるので、実はすぐに1000個を溜められます。 アンタップで大体カードが5枚ほど起きるとしてカウンターは5個。こっから倍にし続けて1000個にするなんて気が遠くなる……と思いますよね? 実際は、5から合計8回倍になれば1280になるので、《世界を救うものまね中、ゴゴ》で7回アンタップ能力をコピーすれば勝てます。つまり14マナですね。本体の起動を合わせると16マナで勝ちです。 そのため《千年暦》で勝つ場合は無限マナは必要ありません。マナがたくさんあればアンタップステップで《千年暦》にカウンターが乗った瞬間にゲームが終わります。 《冷酷な船長、テゼレット》でサーチできたり、無限が決まっていなくとも《世界を救うものまね中、ゴゴ》さえ出ていれば、2ターンをかけて全員を倒せるので、お互いに妨害しあった後の泥仕合を制してくれます。 実際に対戦してみると《千年暦》はかなり強く感じ、オーバーキル気味な勝ち手段だと感じて採用していなかったことを後悔するほどでした。 タップすることで次のターンが飛ぶ代わりに、起動すると追加ターンを得られる土地。 土地枠で勝ち手段になる貴重なカードで、青マナも出ます。 ターンを飛ばした後にターンを得ると、飛ばしたターンが帳消しになるため、追加ターンの起動型能力を《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーすることで、追加ターンをそのまま獲得できます。1回コピーすれば追加1ターン、2回コピーすれば追加2ターンです。 《水の帳、マゴーシ》をタップしてカウンターを置き、《砂時計の侍臣》などでアンタップ。そして起動して《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーするだけなので、少ないマナで無限に入れます。 X=1でコピーするだけで無限ターンとかなり強く、《探検の地図》を入れて《水の帳、マゴーシ》をサーチできるようにしても良いかもしれません。 コンボを助けるカードたち アーティファクトを唱えると手がかりが出て、アーティファクトの起動が軽くなります。《玄武岩のモノリス》と組み合わせての無限マナはもうご存じですね。 手がかりの起動も軽くなるので1マナで引けるようになり、適当なマナファクトがすべてドローになるので、かなりコンボが簡単になります。 アーティファクトが全部《Mox Sapphire》になるだけでなく、無限マナの注ぎ込み先としても優秀。ライブラリーを全部掘れるので、無限マナが決まって《最高工匠卿、ウルザ》がいれば勝ちになります。 手がかりなどのトークンも《Mox Sapphire》になるので、《最高工匠卿、ウルザ》が生き残れば《世界を救うものまね中、ゴゴ》による無限もかなりしやすくなります。出たゲームの勝利貢献度がかなり高いカード。 起動を2マナ軽減するエンチャント。0にはできないので、《世界を救うものまね中、ゴゴ》をタダで起動することはできませんが、X=1分の2マナで2回コピーできます。 無限コンボの際に必要なマナが6マナになります。《世界を救うものまね中、ゴゴ》のバリュー爆上がりです。 クリーチャーが出たターンに起動型能力を使えるようになります。《世界を救うものまね中、ゴゴ》を出したターンに即コンボに移れますし、各種アンタップクリーチャーも出たターンに起動できるので、突然死を生み出せます。 クリーチャーをアンタップする能力も強く、3マナファクトを《砂時計の侍臣》でアンタップし、その《砂時計の侍臣》を《千年霊薬》で起こすことで、マナを増やしたりできます。 《一つの指輪》の次にプライオリティの高いカードで、よくサーチ先になります。 各プレイヤーのアンタップステップにアーティファクトが一緒にアンタップする凄まじいカード。 マナアーティファクトがとりあえず全部起きるので、対戦相手のターンに常にマナを大量に使えるようになりますし、《一つの指輪》がそれぞれ1回ずつ起きるので、自分のターンに1ドローして、ターンが帰ってきた時には9枚引き、カウンターが4個乗った状態で自分のターンを迎えることができます。《求道者テゼレット》のマイナス4で《一つの指輪》とセットで持ってくることの凶悪さがこれでわかるでしょう。 《エルドレインの玉座》で各ターンに2ドローしたり、《多用途の鍵》を組み合わせれば更にアンタップしてアーティファクトを使い回せるので、ドロー手段と一緒に戦場に置いてあれば、次の自分のターンを迎えた時には大体勝ちます。 いずれもアーティファクトをアンタップするカード。《多用途の鍵》には違う能力が書かれていますが、まあ使わないので大丈夫です。 《一つの指輪》を起こして大量ドロー、《エルドレインの玉座》などを起こしてマナを爆発的に増やすなど、まさしく使い方は多用途に渡ります。1ターン目に《太陽の指輪》→《多用途の鍵》と回った時はかなりヘイトを買います。 ただ、アンタップできるのはアーティファクトに限るので、《砂時計の侍臣》などと違って《世界を救うものまね中、ゴゴ》で無限マナを生み出すことはできません。ゴゴを起こせないからです。 《世界を救うものまね中、ゴゴ》がアーティファクトになれば《多用途の鍵》でゴゴを起こせるので、《大変成家、アンクタス》でゴゴをアーティファクトにすることで、ゴゴ+《多用途の鍵》+《大変成家、アンクタス》+3マナファクトで無限マナを作れます。この場合は無限マナ+無限ルーターなのでそのまま勝ちまでいきますね。 マナファクトになったり対戦相手の《一つの指輪》になったり《巻き戻しの時計》を増やしたり。その便利さは計り知れません。 《再利用隔室》からサーチすることもしばしばあり、その役割こそはっきりとはしていないものの、手札にあれば勝利に貢献してくれます。 土地関連 《世界を救うものまね中、ゴゴ》で起動型能力をコピーすることでマナ加速できるので、フェッチランドは入れられるだけ入れてます。《寓話の小道》はタップインですが、土地が2枚の時に3枚目の土地として《寓話の小道》を置くと、片方は4枚目の土地になるのでアンタップします。 他にも《進化する未開地》などがありますが、確定タップインとなるフェッチランドは採用していません。手札にそれしかない時に動きがかなり鈍るためです。 《島》を生け贄にすることになるので《久遠なる栄光の笏》とはアンチシナジーになりますが、それでも強すぎるので入れました。 何せ《砂時計の侍臣》などでアンタップできますからね。実質3マナファクトなので無限にも貢献しますし、かなり強いです。《さびれた寺院》と組み合わせてマナを増やしたり、《一つの指輪》を起動していると、昨年のモダンの相棒を思い出して涙が出そうになります。 主に《睡蓮の原野》を起こすカードですが、《水の帳、マゴーシ》を起こして即無限ターンに突入したり、《水辺の学舎、水面院》を起こして《一つの指輪》を使い回したり、かなり便利。 《さびれた寺院》のアンタップ能力は《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーできます。睡蓮の原野》を起こすなら1回のコピーで1マナ増える計算になります。使うこともあるので一応覚えておいてください。 マリガン とにかくマナ加速のない手札はダメです。《一つの指輪》があるぐらいの手札以外はまずマリガンします。 あるいは《奇怪な宝石》《お告げの行商人》で《世界を救うものまね中、ゴゴ》を4ターン目ぐらいに大きく使えるような手札です。 マナファクトは2枚以上はある方が良いですね。逆にマナしかない手札はかなり強いのでキープです。1回《世界を救うものまね中、ゴゴ》を出してマナさえ余らせておけば、サイクリング1枚が5ドローぐらいになるので、かなり受け入れが広いです。 マナが最優先で、それ以外のカードは二の次。ただし《一つの指輪》だけは強すぎるので、4ターン目に置ける算段が立っているならキープできる。 こんな感じです。 統率者戦は4番手になってしまった場合、かなり敗色濃厚です。生半可な手札では絶対勝てないので、《太陽の指輪》《魔力の櫃》《厳かなモノリス》など、後手をまくれるようなマナ加速でキープしたいです。初手が5枚でも《世界を救うものまね中、ゴゴ》がリソースになってくれるので、手番が遅いなら弱めなハンドはマリガンしましょう。 デッキの回し方 デッキの回し方は単純です。とにかく《世界を救うものまね中、ゴゴ》を使って色んな能力をコピーしましょう。 マナが多ければ多いほどコピーの値が増えるので、まずはフェッチランドを《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーしてマナ加速。そしてサイクリングをコピーして大量にドロー。 こうやって引いたカードで最終的に《一つの指輪》に辿り着いたり、無限コンボを決めていきます。 《加工》などのサーチはほぼ確実に《一つの指輪》になります。無限コンボを決めにいくなら《千年霊薬》でも良かったりしますが、簡単な妨害でコンボを防がれると、一気に勝ちが遠のいてしまいます。《一つの指輪》に触れる手段はさほど多くないので、とりあえず《一つの指輪》を出して、《世界を救うものまね中、ゴゴ》でコピーして大量に引いてゲームを決めにいくのが簡単かつ安全です。 基本の無限パターンはすべて場で完結するので、コンボに向けて何か下準備をする必要はほとんどありません。とりあえず盤面に無限パーツを並べて、そのままターンが帰ってきたらとりあえず始めます。 明らかに全員がマナを構えている状態なら、自分の直前のプレイヤーのエンド時に仕掛けても良いでしょう。そこで《世界を救うものまね中、ゴゴ》を触られても、自分のターンでまたすぐにコンボを始動できます。 コンボの際は《世界を救うものまね中、ゴゴ》が触られることになるので、他のカードは場に残ります。なのでゴゴが速攻を持っていれば次のターンにすぐ仕掛けられます。《千年霊薬》の強みはここにありますね。 無限マナを作る行為自体に手札を使ったりはしないので、割とノーリスクでコンボを始められます。そのためプレイ自体はさほど難しくありません。無限マナを作ろうとすると8マナを使って3マナファクトをアンタップすることになるので、9マナが浮きます。その9マナの使い道が何かあれば更に無駄にならなくて良いですね。 妥協リスト 《厳かなモノリス》や《Transmute Artifact》など、高額カードが一部入っていますが、基本的にはかなり安いデッキです。 なので「FFも好きだしせっかくだから初めてのブラケット4のデッキにしよう」なんて方にもオススメできるのがこのデッキ。とはいえ、5万のカードを突然買うのは厳しいでしょう。 そこで5000円以上のカードを抜いた妥協リストを作ってみました。《一つの指輪》だけは絶対に必要になるので、1万円ぐらいしますが買ってください…!お願いします! 《カワウソボールの精鋭、キッツァ》+《ぐるぐる》や《等時の王笏》+《ぐるぐる》など、《世界を救うものまね中、ゴゴ》を使った基本の無限パターンの種類を増やしています。いずれも《砂時計の侍臣》などのアンタップカードの代わりになるアンタップ手段なので、妥協リストでもかなり無限を楽しめると思います。 まずは上記リストを組んでみて、そこから《意志の力》や《否定の力》といった妨害手段、次に《金属モックス》などの0マナファクト、そして最終的に《厳かなモノリス》《Transmute Artifact》に手をつけてみてください。《Transmute Artifact》は下位互換の《作り直し》でも全然良いと思います。 「デッキに興味は持ったけど高すぎる!」と思った方はぜひこの妥協リストをお試しください。 おわりに というわけで今回は《世界を救うものまね中、ゴゴ》の紹介でした! 一から統率者デッキを作るのってとにかく楽しいですね。カードを見つけて買ってどんどん完成していくのもたまらなくて、カードを買うのがクセになっちゃいそうでした。 最近は大会に出る時はリュックの奥にゴゴを忍ばせているので、機会があったらぜひ遊びましょう! ゴゴにオススメのカードとかがあればぜひ教えてください!@yuyan_mtgにリプライ飛ばしてください!喜びます! それではまた!
WRITER
ライター
-

細川 侑也
-

Akira Kobayashi
-
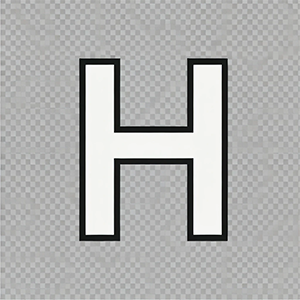
Ryo Hakoda